トピックス
2015年のサンマ漁況を振り返って(1/15)
ここでは、2015年漁期を改めて振り返り、さらに過去2年の状況と比較してサンマの不漁の原因について考察することとしたい。 2015年の日本漁船によるサンマ水揚量は、112,255トン(全さんま発表)であった。2014年(224,755トン)と比較すると水揚量は半分に落ち込んだ。 1973年以降の水揚量と比較すると、2015年は、1976年(9,8036トン)に次ぐ低い量であり、1980年以降で見ると最低である(図1)。1976年と現在を比較すると、 漁船の装備や魚群探索時の情報量に違いがあり、単純には比較できないが、2015年は歴史的な大不漁であったと言える。 2015年の不漁の原因は、サンマの資源量の減少を主因とし、漁場位置と海況の影響、サンマの太り具合、外国船の影響等の要因が複雑に絡み合ったことによるものと 考えられる。
1.サンマの資源量の影響
水産総合研究センターが漁期前に行った表層トロールを使った調査結果から推定した資源量を見ると、
Ⅰ区+Ⅱ区における資源量(漁期中日本漁船が操業する範囲に来遊する可能性がある資源量)は、減少傾向であり、2015年(約136.1万トン)は、
2013年(約180.2万トン)および2014年(約190.5万トン)を下回った。さらにサンマの資源量が減少した2010年以降、日本に近い海域を北上するサンマが少なくなった。
過去にもマイワシの資源量が増加する時にはサンマの資源量が減少することがあったが、2009年頃からマイワシの資源量が増加しており、
サンマの資源量は2000年代後半のような高位水準にはなりにくい状況である可能性がある。資源量の減少が、2015年漁期の不漁の主因であるものと考えられ、
加えて2015年漁期は、資源量の減少率以上に漁獲量が減少したことから、その他の要因について次に考察する。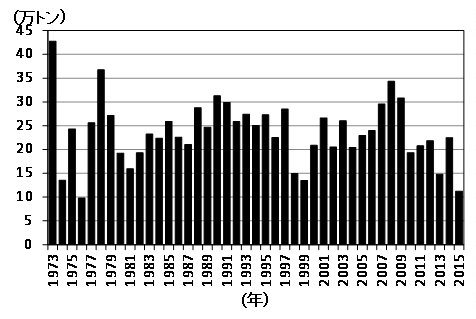 図1 日本漁船によるサンマ漁獲量の推移
図1 日本漁船によるサンマ漁獲量の推移
2.漁場と海況の影響
2015年のサンマ漁場と表面水温分布を旬別に示す(図2)。8月は、過去2年(2013年、2014年)同様、
花咲港から2日程度かかる場所が主漁場であった。過去2年と比較すると、8月としては魚群にあたる船が多かったため、8月の水揚量は過去2年を上回った。
9月上旬になると、花咲港まで日帰り〜1日程度かかる場所が漁場となった。過去2年と比較すると、全般的に魚群が少なかったことから、
漁獲は2013年および2014年を下回るようになった。2015年は、根室の南に暖水塊があり、この暖水塊の西側を暖水が北上して沿岸近くまで張り出していたこともあり、
例年道東沿岸を南下する親潮第一分枝が非常に弱かった。この影響もあり、2014年と比較すると道東沿岸を南下した群は非常に少なかった。
親潮は根室南にある暖水塊の東側を南下するようになり、9月中旬〜10月上旬の主漁場は道東沿岸ではなく、この暖水塊の東〜南東側であった。
つまり千島列島近くを南下した魚群の多くは、道東沿岸ではなく、沖合を通って南下した可能性が高いと考えられる。
10月に入り、日本周辺にサンマの群が非常に少なかったことから、多くの船が公海域で操業するようになった。三陸および道東の港から200〜300海里離れた場所が
主漁場となり、そこでも1晩で満船となる船は少なく、多くの船は2〜3晩操業であった。10月下旬〜11月上旬に、沿岸近くの金華山沖〜常磐北部海域でも漁場が形成
されたものの、小型船主体の漁場であり、魚群は少なかった。このように、10月〜11月は、港からかなり離れた場所が主漁場であった。主漁場まで港から約2日、
漁場で2晩操業、港まで約2日かかると、1週間に1回程度しか水揚できない。2014年は、日本の沿岸を南下する魚群が多かったため、大型船でも日帰り〜2晩で水揚
できる事が多かった。このような状況であったため、2015年の漁獲量と2014年の漁獲量との差が大きくなっていった。
11月に入り、時化が多くなると、公海域での操業が難しくなった。また公海域でも群が少なくなり、漁獲が急激に悪くなった。日本の近海でも群が少なかったことから、
11月下旬で多くの船が漁を切り上げざるを得なくなった。
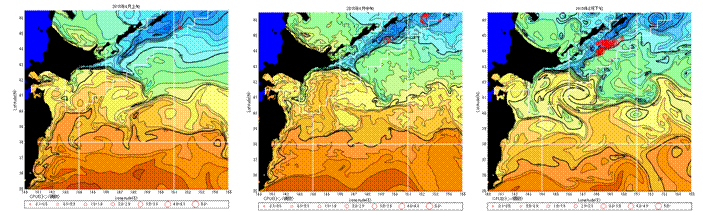
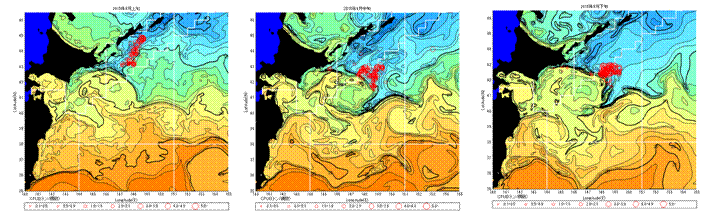
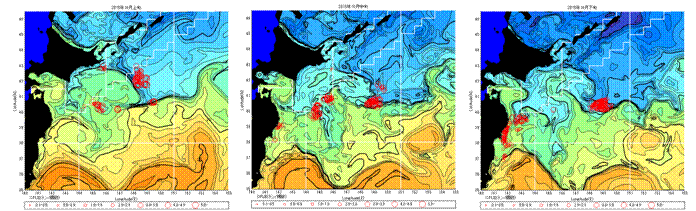
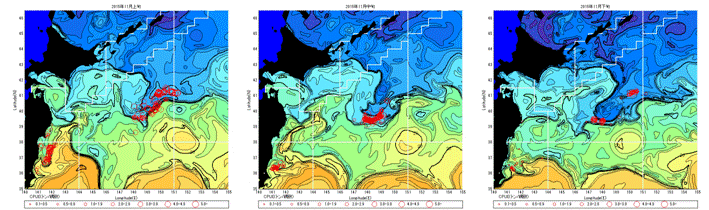 図2 2015年旬別漁場と表面水温分布(8月上旬〜11月下旬)
図2 2015年旬別漁場と表面水温分布(8月上旬〜11月下旬)
3.サンマの太り具合
2015年は、サンマの太り具合が非常に悪かった。例として9月10日に北海道根室市の花咲港に水揚されたサンマの 体長組成と体重組成を示す(図3)。2014年は、体長31cmモード、体重160gモードで、190gや200gを超すサンマもいた。一方2015年は、体長30cmモード、 体重130〜140gモードで、例年生鮮流通の主体となる160g以上の魚は非常に少なかった。このように、2015年はサンマの太りが非常に悪かった。サンマは北の海域で太り、 脂肪を蓄えてから産卵のために南の暖かい海域へ移動する。このことから、2015年はサンマの太りが悪く、サンマの南下が遅くなった可能性がある。
4.外国船の影響
外国船の影響については、大きく2つに分けて考える必要がある。1つは、サンマの資源量の長期変動に与える影響である。 前述の通り、サンマの資源量が減少傾向の中にあって、日本漁船による漁獲量も減少傾向にあるが、外国船による漁獲量は増加傾向であり、結果として全体の漁獲量が 過剰になっているのではないかということである。この件については、北太平洋漁業資源保存条約(NPFC条約)が発効したことから、関係国による国際的な資源管理に 向けた取り組みに期待するところである。 もう1つは、漁期中における外国船による漁獲の影響である。2014年のように、サンマが太っており、沖合から順調に日本周辺に魚群が来遊するような状況では、 外国船による漁獲の影響は少ないと考えられる。しかし、2015年は海況条件やサンマのコンディション(なかなか太らず、南下するようなサンマにならなかったこと) により、日本周辺を南下するサンマが少なかった。このため、10月以降は日本漁船も公海域を含む沖合を南下するサンマを漁獲対象にせざるを得なくなったことから、 公海域で操業する外国船による漁獲の影響を受けたものと考えられる。実際に2015年は、日本漁船が公海域で操業する際、外国船の漁場と重なることも多かった。
5.最後に
日本漁船によるサンマの漁獲量は、サンマの資源量および北上期の資源の分布状況、海況、サンマの状態(太り具合など)の
影響を大きく受ける。さらに2015年のように、沖合から日本周辺への魚群の来遊状況が悪い時は、特に漁期後半、公海域での外国船による漁獲の影響が大きくなる。
このように、様々な要因が複雑に絡み合うことから、今後、資源量調査の状況や、日々の海況や漁況、漁場の動向等に注目することが必要である。
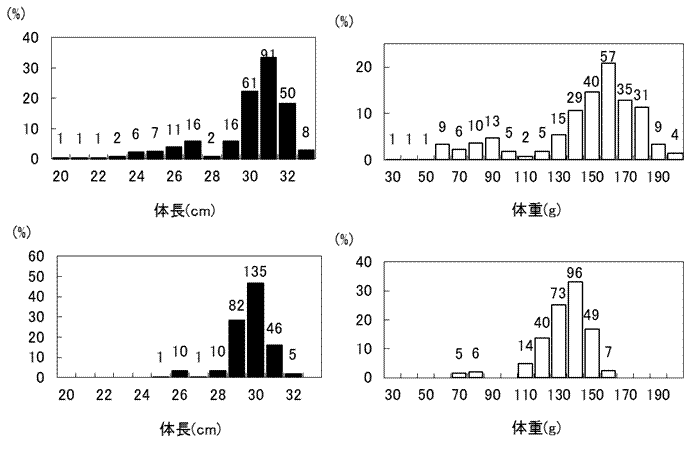 図3.9月10日花咲港水揚物の体長組成と体重組成
(左側:体長組成、右側:体重組成、上段:2014年、下段2015年)
図3.9月10日花咲港水揚物の体長組成と体重組成
(左側:体長組成、右側:体重組成、上段:2014年、下段2015年)