トピックス
常磐沖のサバ漁南下進む(11/11)
銚子は4日間で9700トン
 三陸〜常磐沖のサバまき網漁場は、前月より引き続き金華山沖に形成されていますが、月末からは日立沖にも形成されたほか先週末は鹿島沖にも形成され、南下が徐々に進んでいます。今年の8〜9月の道東沖では400〜600gのマサバ主体に2万トンの漁獲と久々に好漁だったものの、八戸沖ではマサバがほとんどいなくゴマサバ主体に1万トンの漁獲と明暗が別れました。銚子の10月中のさば類の水揚げは1日に数百トン〜1,500トン程度でしたが、10月29日2,512トン、31日2,212トンと月末に急増し、10月合計水揚量は10,736トンでした。
11月は1日に3,036トン、3日に3,302トン、5日に1,804トン、6日に1,591トンと4日間で9,733トンを記録しており、4日間の水揚げで10月の1ヶ月に匹敵する好漁でした。
三陸〜常磐沖のサバまき網漁場は、前月より引き続き金華山沖に形成されていますが、月末からは日立沖にも形成されたほか先週末は鹿島沖にも形成され、南下が徐々に進んでいます。今年の8〜9月の道東沖では400〜600gのマサバ主体に2万トンの漁獲と久々に好漁だったものの、八戸沖ではマサバがほとんどいなくゴマサバ主体に1万トンの漁獲と明暗が別れました。銚子の10月中のさば類の水揚げは1日に数百トン〜1,500トン程度でしたが、10月29日2,512トン、31日2,212トンと月末に急増し、10月合計水揚量は10,736トンでした。
11月は1日に3,036トン、3日に3,302トン、5日に1,804トン、6日に1,591トンと4日間で9,733トンを記録しており、4日間の水揚げで10月の1ヶ月に匹敵する好漁でした。
マサバ主体の漁獲
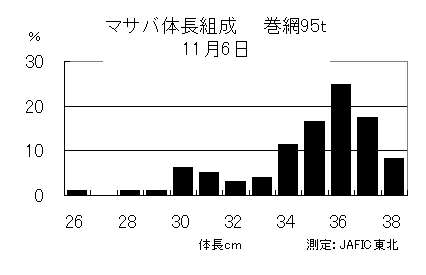 7日に石巻(金華山沖漁場)で水揚げしたものはマサバが99%・ゴマサバ1%とマサバが大半を占め、体長33cm(500g)台以上の大型のマサバが5割強〜8割強と大型魚主体でした。
32cm未満の中小サバには日によってはゴマサバが半分混じっているようです。粗脂肪量は600g以上のマサバでは17〜28%、400〜600gでは15〜22%とまずまずのようです。
7日に石巻(金華山沖漁場)で水揚げしたものはマサバが99%・ゴマサバ1%とマサバが大半を占め、体長33cm(500g)台以上の大型のマサバが5割強〜8割強と大型魚主体でした。
32cm未満の中小サバには日によってはゴマサバが半分混じっているようです。粗脂肪量は600g以上のマサバでは17〜28%、400〜600gでは15〜22%とまずまずのようです。
2013年生まれは期待
先日銚子漁協で開催した食と漁のシンポジウムでは、研究者の発表によると2013年生まれの当歳魚は、高水準だった1980年代に匹敵する高い加入量とのことで、現在はまだ小さい(100〜200g)ものの鮮魚向けとなる中・大サバになる来年以降に 期待できるようです。ただ、現在漁獲の主体は1歳魚(2012年生まれ)の300g級と3歳魚(2010年)以上の500g級に600g級混じりで、2歳魚(2011年)はほとんど漁獲対象となっていいないとのことです。 これからシーズンとなる東シナ海では済州島の東側で操業があるものの、マサバローソクやゴマサバローソクが大半で、マサバの大型は少ないようです。盛漁期に入るのは もう少し時間がかかりそうです。