トピックス
サンマ、ようやく南下が本格化(10/22)
ようやく道東に漁場
 今年のサンマ漁は、大型魚が沖合にしかいないことから、昨年同様に例年より沖寄り(東寄り)の漁場形成となった。漁場までの距離が遠いことに加え、解禁も1週間程度遅くなったことから、9月中旬まで水揚げの伸びを欠いていた。全さんま所属船の大型船が8月20日に解禁になって以降、初漁期は昨年同様にウルップ島南島沖に漁場が形成され、その後、エトロフ島沖と徐々に近づくも引き続き片道1日以上の航海を要した。9月下旬〜10月上旬になって、ようやく色丹島南東沖まで漁場が南下し、根室・花咲港から片道半日程度の距離となった。先週から道東沿岸や三陸沖合にも漁場が形成されるようになり、10月20日をもって、ロシア主張200海里水域内の操業が終わった。
今年のサンマ漁は、大型魚が沖合にしかいないことから、昨年同様に例年より沖寄り(東寄り)の漁場形成となった。漁場までの距離が遠いことに加え、解禁も1週間程度遅くなったことから、9月中旬まで水揚げの伸びを欠いていた。全さんま所属船の大型船が8月20日に解禁になって以降、初漁期は昨年同様にウルップ島南島沖に漁場が形成され、その後、エトロフ島沖と徐々に近づくも引き続き片道1日以上の航海を要した。9月下旬〜10月上旬になって、ようやく色丹島南東沖まで漁場が南下し、根室・花咲港から片道半日程度の距離となった。先週から道東沿岸や三陸沖合にも漁場が形成されるようになり、10月20日をもって、ロシア主張200海里水域内の操業が終わった。
累計量は2010年並
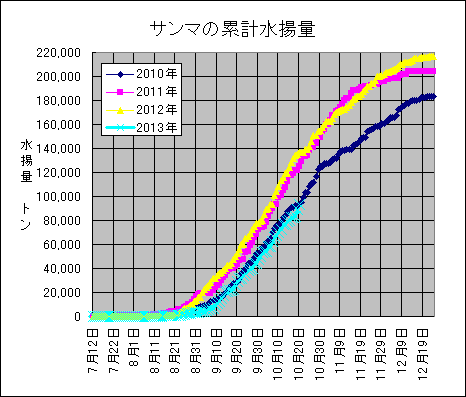 10月20日現在の水揚累計は93,407トンで、2012年同期の136,3698トン(12月末の漁期累計で21万8371トン)、2011年同期の124,637トン(同20万7770トン)と比べ3〜4万トン少なく、不漁だった2010年同期の93,644トン(同19万3425トン)並みの水準となっている。近年では1998年が14万トン、99年が13万5千トンと大不漁だったが、2000〜2006年は20〜26万トンと安定し、その後、公海域に数百万トンの膨大な資源があるとのことでミール向けを含むTACを増枠したことから2007年は29万6千トン、2008年は18年ぶりに30万トンを超える34万3千トンに急増し、2009年は30万8千トンと2年続けて30万トン台を記録。その後、2010年は不漁で10万トン以上減り、19万3千トンと落ち込んだ。
10月20日現在の水揚累計は93,407トンで、2012年同期の136,3698トン(12月末の漁期累計で21万8371トン)、2011年同期の124,637トン(同20万7770トン)と比べ3〜4万トン少なく、不漁だった2010年同期の93,644トン(同19万3425トン)並みの水準となっている。近年では1998年が14万トン、99年が13万5千トンと大不漁だったが、2000〜2006年は20〜26万トンと安定し、その後、公海域に数百万トンの膨大な資源があるとのことでミール向けを含むTACを増枠したことから2007年は29万6千トン、2008年は18年ぶりに30万トンを超える34万3千トンに急増し、2009年は30万8千トンと2年続けて30万トン台を記録。その後、2010年は不漁で10万トン以上減り、19万3千トンと落ち込んだ。
5千トンを超える水揚げも
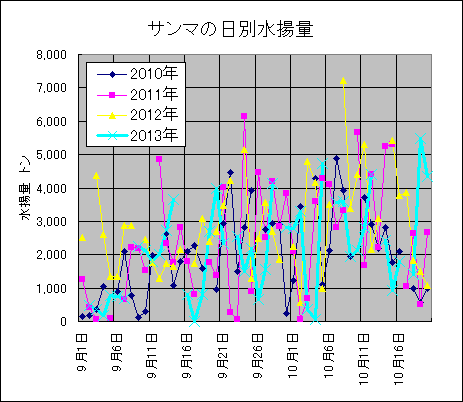 今年のサンマの日別水揚げ量は、8月以降、9月7日までは数百トン止まりと低調。9月9日と10日にようやく2千トンにのった。台風の通過や休漁措置もあり、水揚げの増減を繰り返しながら9月14日に3,647トンを、20日に3,993トンを記録。10月5日には5千トンに迫る4,746トンを、10月19日にようやく5,482トンの大台にのった。10月20日現在の市場別累計水揚量は、漁場に一番近い根室の花咲が49,997トン(前年69,623トン)で、全国合計の半分を超える54%と昨年同期に51%とウエイトが高く、厚岸と釧路が昨年の半分の水揚げとなり、各10%。三陸〜常磐は2万2700トンと6千トンほど減らしたものの、全体が3割減ったことから20%から24%と増加。
最近の相場は魚体組成により異なり、道東では大型2割なら平均でキロ130〜150円だが、大型1割なら50〜70円。三陸は概ね150円前後で水揚げが少ないと10月中旬でも300円近い日もある。10月の平均は124円で、昨年の61円の倍。不漁だった2010年の103円の2割高。
今年のサンマの日別水揚げ量は、8月以降、9月7日までは数百トン止まりと低調。9月9日と10日にようやく2千トンにのった。台風の通過や休漁措置もあり、水揚げの増減を繰り返しながら9月14日に3,647トンを、20日に3,993トンを記録。10月5日には5千トンに迫る4,746トンを、10月19日にようやく5,482トンの大台にのった。10月20日現在の市場別累計水揚量は、漁場に一番近い根室の花咲が49,997トン(前年69,623トン)で、全国合計の半分を超える54%と昨年同期に51%とウエイトが高く、厚岸と釧路が昨年の半分の水揚げとなり、各10%。三陸〜常磐は2万2700トンと6千トンほど減らしたものの、全体が3割減ったことから20%から24%と増加。
最近の相場は魚体組成により異なり、道東では大型2割なら平均でキロ130〜150円だが、大型1割なら50〜70円。三陸は概ね150円前後で水揚げが少ないと10月中旬でも300円近い日もある。10月の平均は124円で、昨年の61円の倍。不漁だった2010年の103円の2割高。
11月は三陸が主漁場
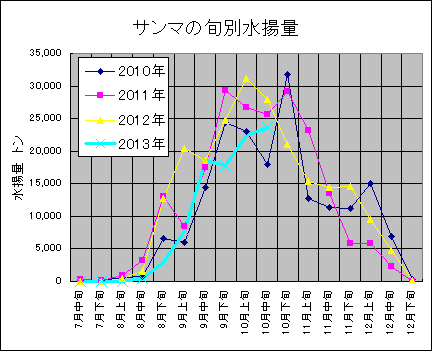 旬別水揚量では9月下旬〜10月下旬がピークとなるが、今年の10月上旬で1万トン、中旬で5千トン少ない。これからも台風の通過が多いが、巻き返しに期待したい。なお、JAFICが公表したサンマ中短期漁況予報(10月下旬〜12月上旬)では、道東海域の来遊量は減少して11月上旬に終漁し、三陸海域の来遊量は増加して11月上〜下旬は中位水準に、常磐海域では10月下旬となる断続邸な来遊があり11月中旬〜12月上旬は中位水準となる見通し。詳細は下記のURLをご覧ください。
旬別水揚量では9月下旬〜10月下旬がピークとなるが、今年の10月上旬で1万トン、中旬で5千トン少ない。これからも台風の通過が多いが、巻き返しに期待したい。なお、JAFICが公表したサンマ中短期漁況予報(10月下旬〜12月上旬)では、道東海域の来遊量は減少して11月上旬に終漁し、三陸海域の来遊量は増加して11月上〜下旬は中位水準に、常磐海域では10月下旬となる断続邸な来遊があり11月中旬〜12月上旬は中位水準となる見通し。詳細は下記のURLをご覧ください。