トピックス
カツオとサンマの水揚げ
カツオ漁
カツオ漁とサンマ漁が終盤を迎えている。カツオ漁は、例年、夏場以降、漁場が三陸沖に移る。夏〜秋期の鰹竿釣船の重要な水揚港である気仙沼港は、震災で被災し、市場施設・関連施設の復旧も今期の水揚げまでに間に合うか危惧された。気仙沼では6月28日から旋網によるカツオの水揚げが始まり、7月13日にようやく竿釣船の水揚げも始まった。
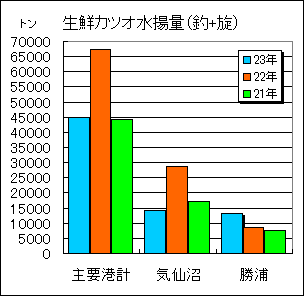 当初、漁に使う餌の活きたカタクチイワシの不足や氷等の不足や出荷体制の関係で、水揚げを1日50トンに制限していたが徐々に水揚げを増やすことができ、9月には竿釣だけで400トンを水揚げする日もみられ、盛り返した。生鮮カツオの主要港の水揚げも、10月末までの累計では千葉の勝浦の水揚げが気仙沼を若干上回っていたものの、11月21日現在では気仙沼が勝浦を800トン上回り、今年も生鮮カツオの水揚げ日本一が確実視される。
当初、漁に使う餌の活きたカタクチイワシの不足や氷等の不足や出荷体制の関係で、水揚げを1日50トンに制限していたが徐々に水揚げを増やすことができ、9月には竿釣だけで400トンを水揚げする日もみられ、盛り返した。生鮮カツオの主要港の水揚げも、10月末までの累計では千葉の勝浦の水揚げが気仙沼を若干上回っていたものの、11月21日現在では気仙沼が勝浦を800トン上回り、今年も生鮮カツオの水揚げ日本一が確実視される。
今期の主要港の生鮮カツオの水揚げ(まき網含む)は、45,048トン(11/21現在)で昨年の67,338トンを2万2千トン下回るものの、不漁年であった一昨年の44,274トンを若干上回る水準。気仙沼は14,105トンで昨年の28,804トンのほぼ半分。勝浦は13,233トンで昨年の8,658トンのほぼ倍増。銚子は4,608トンで昨年の642トンから大幅に増えた。
サンマは・・・
一方、サンマ漁は親潮の勢力が弱く、表面水温の平年差も高めに推移していることもあり南下が遅れている。現在の南下群の先端は、北緯39度〜40度の大船渡〜宮古沖に留まっている。道東(釧路・厚岸・花咲)の水揚げも11月に入ると例年終えるが、今期は11月中旬(花咲14日、釧路18日)も続いた。根室の花咲港では例年5万トン前後の水揚げであるが、今期は11月21日末現在で7万8千トンと漁場との関係等で水揚げが集中し、過去最高を記録した。
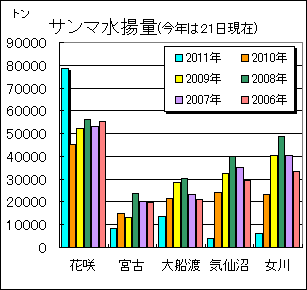 本州では、21日現在の累計水揚量で、宮古8千500トン、大船渡1万4千トン、気仙沼3千800トン、女川6千200トンと、岩手県と宮城県で倍以上の差がついている。TACの消化状況で11月中に終漁となることが多かったが、近年、資源量を考慮してTACの漁獲枠の増加により、12月20日頃まで漁期が伸びている。今年のサンマの水揚げの特徴としては、漁場と処理能力の関係から道東へ水揚げが集中して本州が大幅に減った、本州でも復興過程によって水揚げの市場間格差が生じたことなどがあげられる。漁場はまだ岩手県沖と北寄りだが、南下が一気に進むようならば時期的にも終漁となるだろう。
本州では、21日現在の累計水揚量で、宮古8千500トン、大船渡1万4千トン、気仙沼3千800トン、女川6千200トンと、岩手県と宮城県で倍以上の差がついている。TACの消化状況で11月中に終漁となることが多かったが、近年、資源量を考慮してTACの漁獲枠の増加により、12月20日頃まで漁期が伸びている。今年のサンマの水揚げの特徴としては、漁場と処理能力の関係から道東へ水揚げが集中して本州が大幅に減った、本州でも復興過程によって水揚げの市場間格差が生じたことなどがあげられる。漁場はまだ岩手県沖と北寄りだが、南下が一気に進むようならば時期的にも終漁となるだろう。