トピックス
水産物の税率
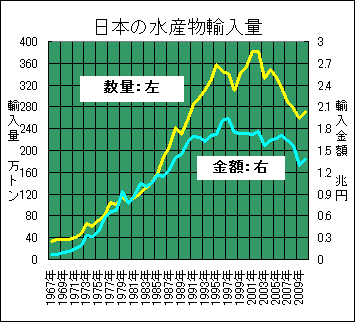 野田首相が、アセアンで環太平洋経済連携協定(TPP)に参加表明ということでいろいろ話題になっています。話題の中心は農業や医療で、水産の話はあまりでてきません。そこで水産物の輸入状況をみてみましょう。輸入量はグラフのようにバブル期の80年代後半に200万トンを超え、90年代には300万トンに達し、2000年代初頭には380万トンとピークを迎え、その後減少に転じます。2009年には250万トン台とピーク時よりも130万トンも少ないレベルで、2010年は272万トンと若干増加しました。金額ベースでは96−97年の1.9兆円から09−10年は1.3兆円と昭和年代末の水準に減りました。このように数量・金額とも現在は20年近く前の水準に戻ってしまったわけです。
野田首相が、アセアンで環太平洋経済連携協定(TPP)に参加表明ということでいろいろ話題になっています。話題の中心は農業や医療で、水産の話はあまりでてきません。そこで水産物の輸入状況をみてみましょう。輸入量はグラフのようにバブル期の80年代後半に200万トンを超え、90年代には300万トンに達し、2000年代初頭には380万トンとピークを迎え、その後減少に転じます。2009年には250万トン台とピーク時よりも130万トンも少ないレベルで、2010年は272万トンと若干増加しました。金額ベースでは96−97年の1.9兆円から09−10年は1.3兆円と昭和年代末の水準に減りました。このように数量・金額とも現在は20年近く前の水準に戻ってしまったわけです。
農水産品の税率をみてみましょう。牛の暫定税率が38.5%(基本50%)、他の基本税率は豚10%、鶏14%、小麦65円/kg、米402円/kg、小豆417円/kg、乳製品は35%+1360円/kgと高めに設定されています。一方、水産物の輸入の税率は、サケ・マグロ・カジキ・メロ・カレイ・ウナギ等の魚類の大半は基本5%、WTO協定加盟国3.5%。後発国の産業振興のための特恵税率では畜産や一部農産品同様に無税です。
カニやエビは基本4−6%で、WTO加盟国1−5%。マイワシ・サバ・ニシン・タラなど、日本国内の漁獲量の多いものは、輸入の上限の枠がある『IQ品目』として10%とやや高めに設定されています。イカ・タコ・カキ・ホタテ等も同様で10−15%、魚類でも魚卵・塩乾品・燻製品は15%、WTO加盟国ではともに3.5−7%といったところ。海藻では海苔が1.5円/枚、アマノリが40%と高め、ヒジキ・ワカメが15%でWTO加盟国だと10.5%、寒天が基本160円/kgでWTO加盟国112円/kg。魚類の調製品も大方10%、エビ・カニの調製品は5%、イカの調製品は15%、ヒジキの調製品は20%前後。養殖魚や養鶏の配合飼料に使用する魚粉・ミールは無税、真珠も原料は無税ですが加工されると6.2%。
WTO(世界貿易機関)の加盟国は153ヶ国で、大半の国は既に加盟済みです。加盟申請中がロシア・カザフスタン等の旧ソ連諸国、アフガニスタン・イラン・イラク等の中近東諸国、アルジェリア・赤道ギニア・エチオピア・シリア等のアフリカ諸国やセルビア・ラオス・ブータンなど約30ヶ国。一方、非加盟国は北朝鮮・東ティモール・南スーダン等、わずか15ヶ国だけです。
日本が輸入する場合には、基本の税率が適応される場合は少なく、先進国の場合はWTO加盟国の税率が適応されるので大方3.5%で、エビだと1%、IQ品目や加工品等でも7−10%と、農産品に比べると税率は低いようです。また、後発国の産業振興のための関税が無税の特恵国はアジア・アフリカ・東欧・太平洋等諸国等、137ヶ国47地域もあります。日本での水産物輸入量の特に多い、中国(2010年の水産物輸入金額1位・46.5万トン・2419億円)、タイ(2位・21.4万トン・1127億円)、チリ(4位・2312万トン・1098億円)、インドネシア(7位・1239万トン・748億円)、ベトナム(8位・1361万トン・717億円)も特恵国で、基本的に関税無税です。WTO加盟国・特恵国も含め、水産に関していえば、とっくの昔に貿易の自由化の状態です。水産物の輸出・輸入の多寡の要因は、円高・円安による為替やデフレによる商品価格の低迷(価格に転嫁できないので輸入できない=買い負け)等の問題の方が、税率云々より効いているように思えます。