トピックス
サンマ漁況予報公表
独立行政法人水産総合研究センター東北区水産研究所が、平成21年度北西太平洋サンマ長期漁海況予報の結果を公表した。概要は以下のとおり。(1)来遊量:来遊量は前年を下回る。(2)魚体:漁期始めは大型魚が主体であるが、漁期中盤からは中小型魚の割合が増加する。漁期全体では前年に比べ中小型魚の割合が増加する。(3)漁期・漁場:大型船出漁後の漁場は、道東沖から色丹島沖に形成される。三陸沖への南下時期は平年より1旬早く、漁場形成は9月下旬になる。
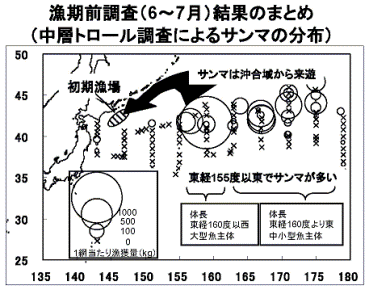
日本近海から西経165゚までの資源量の経年変動は、2003年以降、800万トン、466万トン、430万トン、447万トン、440万トン、483万トンであり、2004年以降安定。一方、日本漁船によるサンマの水揚量は2003年以降、26.0万トン、20.5万トン、23.0万トン、24.0万トン、29.5万トン、34.3万トンと推移。また、総水揚数量の60%以上を漁獲する100トン以上の大型船によるCPUE(1網当たり)は2003年以降、2.9トン、3.2トン、5.7トン、5.2トン、6.0トン、7.0トンと上昇傾向。以上より北西太平洋のサンマの資源状態は高位で安定、漁場への来遊状況も良好であった。
 (1)来遊量
(1)来遊量
漁期前のサンマの分布は毎年東経155゚以東で多い。また、サンマ棒受網漁船のCPUEは9月〜10月にピークとなる。このことから6月〜7月の沖合に分布していたサンマ群が、棒受網漁船の盛漁期に漁場へ来遊していると考えられる。漁期前調査の結果ではサンマの分布は今年も東経155゚以東で多く、推定資源尾数は前年を上回ったものの、今年は大型魚の割合が16.4%と前年(61.1%)に比べ低く、推定資源量は351万トンと前年を下回った。このことから、来遊量は前年を下回る。
(2)魚体
漁期前調査では、東経160゚以西では大型魚主体で、東経160゚より東では中小型魚の尾数が非常に多かった。調査海域全域の大型魚の割合は16.4%で、前年(61.1%)を大きく下回り、2002年以降では最も低かった。漁期前に東経155゚以東に分布していたサンマは漁期になると日本近海に来遊することから、漁期始めは、漁期前に東経160゚以西に分布していた大型魚主体群が漁場へ来遊し、漁期中盤以降は、漁期前に東経160゚より東に分布していた群が来遊する。このため、漁期の経過とともに中小型魚の割合は増加し、漁期全体では前年に比べ中小型魚の割合が大きく増加。
(3)漁期・漁場
近年の8月下旬における漁場の平均表面水温は15℃前後で、7月下旬現在の道東沖漁場では表面水温11℃〜13℃で漁獲されている。今年の道東海域の表面水温は前年と比べ低めで、気象庁の予報では8月下旬の道東海域の表面水温は平年と比べ低めになると予測。大型船出漁後の初期漁場は前年よりやや南側の道東沖から色丹島沖に形成されると予測。三陸海域の平均初漁場形成日は10月上旬で、前年も同様。海況予報では9月下旬における襟裳岬南の親潮第1分枝の張り出しは平年並みでありさらに南南西の三陸沖には冷水域が存在する。また三陸沖にはサンマの南下を阻む暖水塊は存在しないことから、三陸海域へのサンマの南下は前年よりもやや早いと考えられ、三陸海域における初漁場の形成は前年より早く9月下旬となる。