トピックス
JAFIC漁業研究会開催
 漁業情報サービスセンター(JAFIC)では、既存の業務内容を見直して新規ユーザーを開拓するために、この4月にプロジェクトチームを立ち上げた。このプロジェクトチームの技術専門員には、長年、茨城県水産試験場でカツオの研究を行ってきた二平章氏(現、茨城大学地域総合研究所 客員研究員)を迎えた。最新の漁業に関する情報を業界関係者に広めるために、二平技術専門員の発案によって漁業情報研究会を定期的に開催することとなり、6月3日の1回目を皮切りにこの1ヶ月間に3回続けて開催した。
漁業情報サービスセンター(JAFIC)では、既存の業務内容を見直して新規ユーザーを開拓するために、この4月にプロジェクトチームを立ち上げた。このプロジェクトチームの技術専門員には、長年、茨城県水産試験場でカツオの研究を行ってきた二平章氏(現、茨城大学地域総合研究所 客員研究員)を迎えた。最新の漁業に関する情報を業界関係者に広めるために、二平技術専門員の発案によって漁業情報研究会を定期的に開催することとなり、6月3日の1回目を皮切りにこの1ヶ月間に3回続けて開催した。
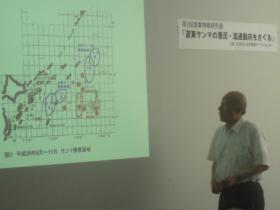 第1回目はカツオをテーマに開催し、JAFICの二平章技術専門員が「日本近海に来遊するカツオの生物特性」と題した講演を行なった。講演内容はこの5月に東京水産振興会が刊行した『月刊水産振興 第497号 カツオの回遊生態と資源』をベースにしたもの。日本に現れるカツオの体長群は5つあり、春生まれと夏生まれがあるという。日本近海では、夏生まれのD群(40〜45cm・1.2〜1.5kg)は夏に現れ、翌年の春にB群(45〜50cm・1.7〜2.0kg)として出現。冬生まれのE群(40cm以下・1kg以下)は夏に現れ、翌年の春にはC群(40〜45cm・1.2〜1.5kg)として出現し、翌々年の春にはA群(50〜55cm・3kg)として出現。D群・E群は黒潮前線を越えて常磐〜三陸沖の亜寒帯域に入るが、B群・C群は黒潮前線を越えるものと越えないものがあるが、大型のA群は黒潮前線を越えないでそのまま南下する。北上ルートは複数あるが、近年、黒潮ルートで北上する群れが減っている。中南漁場では1970年代は黒潮源流域にあたる東経125度付近に漁場形成されたが、1990年代はこの海域の魚が減って東経140度・150度付近と漁場が東寄りに移っている。この要因として海外の冷凍まき網船の漁獲が1980年代以降に急増したことが挙げられると指摘。産卵量でみると1970年代は4歳以上の高齢の夏産卵魚が多かったが1990年代になると激減して、2・3歳の冬産卵魚主体となった。人間は高齢出産だが、カツオは資源を維持するために早期成熟化している、と例えた。
第1回目はカツオをテーマに開催し、JAFICの二平章技術専門員が「日本近海に来遊するカツオの生物特性」と題した講演を行なった。講演内容はこの5月に東京水産振興会が刊行した『月刊水産振興 第497号 カツオの回遊生態と資源』をベースにしたもの。日本に現れるカツオの体長群は5つあり、春生まれと夏生まれがあるという。日本近海では、夏生まれのD群(40〜45cm・1.2〜1.5kg)は夏に現れ、翌年の春にB群(45〜50cm・1.7〜2.0kg)として出現。冬生まれのE群(40cm以下・1kg以下)は夏に現れ、翌年の春にはC群(40〜45cm・1.2〜1.5kg)として出現し、翌々年の春にはA群(50〜55cm・3kg)として出現。D群・E群は黒潮前線を越えて常磐〜三陸沖の亜寒帯域に入るが、B群・C群は黒潮前線を越えるものと越えないものがあるが、大型のA群は黒潮前線を越えないでそのまま南下する。北上ルートは複数あるが、近年、黒潮ルートで北上する群れが減っている。中南漁場では1970年代は黒潮源流域にあたる東経125度付近に漁場形成されたが、1990年代はこの海域の魚が減って東経140度・150度付近と漁場が東寄りに移っている。この要因として海外の冷凍まき網船の漁獲が1980年代以降に急増したことが挙げられると指摘。産卵量でみると1970年代は4歳以上の高齢の夏産卵魚が多かったが1990年代になると激減して、2・3歳の冬産卵魚主体となった。人間は高齢出産だが、カツオは資源を維持するために早期成熟化している、と例えた。
第2回目はサンマをテーマに開催し、JAFIC道東出張所の小林喬所長等が講演を行った。小林所長によると台湾船の現在の漁模様や日本の調査船の調査結果をみると、漁獲が低調で大型魚が少ないことに加え、痩せている魚が多いという。三陸の定置網ではそこそこ獲れているものの沖合資源とは別で、先の結果を踏まえると、今年の漁は良くないのではと予測。養殖魚の餌需要を睨み、国は今年のTAC(漁獲可能量)を昨年並みの45万5千トンとし、日本の領海外に膨大なサンマ資源があるとされるものの、東経170度といった沖合の群れは、日本近海には来遊しないので漁獲対象とはならない可能性が大きいと結論づけた。
 会場には銚子の出荷業者も来ており、解凍サンマを1尾20円台とか40円台で売る採算を無視した今の量販店のやり方を痛烈に批判。出荷業者が量販店と取引する場合、まず、量販店は売値ありきで出荷業者のコストを考慮せずに、量販店が決めた値段でないと取り引きしない。量販店は仕入れ値に自分の利益をのせて確保するので損はしないが、そのしわ寄せは出荷業者や漁業者にいくことになる。この出荷業者によると量販店が魚を貸してくれていって貸しても、返して貰った試しがないそうだ。仲間内でも量販店と取引をして潰された業者も多く、この業者の方も量販店の取引を止めて売上げが6割落ちたものの、なんとかやって行けているそうだ。次回の第3回目の要旨は後日掲載する。
会場には銚子の出荷業者も来ており、解凍サンマを1尾20円台とか40円台で売る採算を無視した今の量販店のやり方を痛烈に批判。出荷業者が量販店と取引する場合、まず、量販店は売値ありきで出荷業者のコストを考慮せずに、量販店が決めた値段でないと取り引きしない。量販店は仕入れ値に自分の利益をのせて確保するので損はしないが、そのしわ寄せは出荷業者や漁業者にいくことになる。この出荷業者によると量販店が魚を貸してくれていって貸しても、返して貰った試しがないそうだ。仲間内でも量販店と取引をして潰された業者も多く、この業者の方も量販店の取引を止めて売上げが6割落ちたものの、なんとかやって行けているそうだ。次回の第3回目の要旨は後日掲載する。