トピックス
金沢沖のスルメ釣り漁本格化
生鮮スルメイカ漁は3〜4月の端境期を経て、ようやく4月末から金沢沖の操業が本格化して水揚げが急増した。
3〜4月の端境期は魚群が産卵の為に南下することから主漁場が山陰以西〜東シナ海北部と狭く、全国的に水揚げが少ない時期にあたる。昨年の秋に東シナ海で産まれた稚いかの群れが、水温の昇温とともに成長しながら日本海を北上し、ようやく能登半島西岸の金沢沖でまだ小さいながらも漁獲できるサイズに達した。例年、この時期になると長崎県の旅船を中心に全国の小型いか釣り船が能登半島沖に集結し、金沢港の水揚げが急増する。金沢港の入港船は4月29日は22隻、4月30日と5月1日は各9隻、5月3日は63隻で6日は113隻と百隻を越えた。5月1日は発泡2千245箱(1箱5kg前後入)だったが、3日には8千815箱、6日は7千664箱と急増。20尾入サイズの大型魚は1%前後、25尾入サイズの中型魚は5〜15%と少なく、30尾入サイズの小型魚は5月1日以前は3割程度であったが、3日には4割を越え、6日には5割を越えた。一方、バラは5月3日以前は6〜5割と大半を占めていたが、6日には3割以下に低下した。
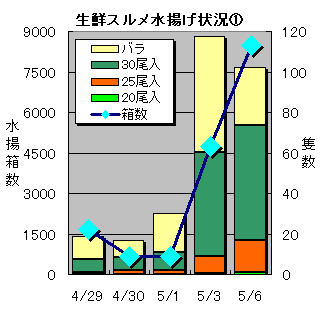
一隻あたりの水揚箱数でみると、入港隻数が9隻と少なかった4月30日の141箱から5月1日の249箱と倍増してピークを迎え、操業隻数が63隻に増えた3日は140箱に半減し、さらに113隻に増えた6日は68箱と低下した。ここ数日の主漁場は能登半島西岸の羽昨〜金沢〜小松沖で、北上の先端は能登半島北岸の輪島沖の模様。
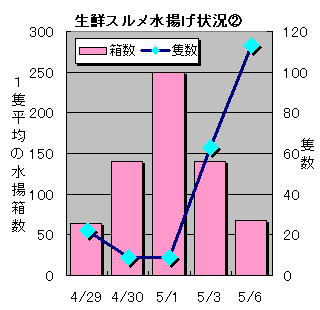
能登半島沖にしばらく滞留したスルメイカの群れは、昇温とともに新潟〜佐渡沖、山形〜秋田沖でも操業が始まり、6月に入ると道南でスルメイカ漁が解禁になる。
独立行政法人水産総合研究センター・日本海区水産研究所が4月28日に公表した第1回日本海スルメイカ長期漁況予報(5〜7月)によると、来遊量は過去5年平均並み、漁期・漁場は昨年より早く過去5年平均並み、魚体の大きさも昨年より大きく過去5年平均並みという。ここ2年間は産卵時期の遅れから小さいものが多かったが、大きさは例年並みに戻ったようである。
水産総合研究センターHPへリンク http://abchan.job.affrc.go.jp/gk21/20090428.pdf