トピックス
消費者の食の志向は経済性重視
日本政策金融公庫・農林水産事業本部(旧:農林漁業金融公庫)は、消費者の「食の志向」「国産食品と輸入食品の購入に関する意識と実態」等について調べた、平成20年度第3回「消費者動向調査」び結果概要を公表した。昨年は食に対する不安や関心が高まりをみせ、昨年5月の本調査では食の安全への志向の高まりや国産品プレミアムの上昇という結果に現れた。その後百年に一度という金融危機に端を発する不況の波が押し寄せており、消費者の食への志向、国産食品と輸入食品に関する意識はどう影響されているのかを明らかにするため、2008年12月に、全国の20〜60代の男女2,107人を対象に、インターネットで調査を行った。 「経済性」への志向が前回調査(平成20年5月)に比べ上昇(平成18年調査27.2%→今回34.6%)して最上位となり、逆に「安全志向」は低下(41.3%→31.7%)した。ただし今後の志向については「安全性」と答える消費者が最も多かった(41.7%)。 食品に関する情報の中で最も関心があるのは「価格」(48.7%→49.8%)で、次いで「生産履歴などの安全性」(33.9%→43.5%)、「産地や美味しい店・旬のもの」(42.6%→35.2%)の順。若い年代ほど「価格」に関心が高く、中高年ほど「生産履歴などの安全性」に関心が高かった。
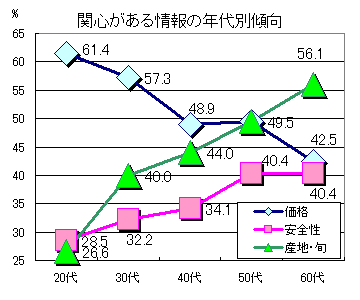 食品の妥当な価格水準については、消費者は調査対象品目のすべてで値下げを要望していた。国産品の輸入品に対するプレミアムは若干減少。国産品の輸入品に対する価格許容度については、鮮魚では「3割を越えても国産品を選ぶ」が10.9%、「3割高までなら国産品を選ぶ」が4.7%、「2割までなら国産品を選ぶ」が16.0%、「1割までなら国産品を選ぶ」が19.3%、「同じ値段なら国産品を選ぶ」が37.4%「国産へのこだわりはない」が11.7%。
中国からの輸入食品については「安全性に問題」が92.4%と前回調査(平成20年5月調査、90.3%)よりも上昇。消費者のイメージは前回調査と同様に、中国・アジア(中国以外)・アメリカは「安いが安全面に問題」、EU・北欧は「安全だが高い」、オーストラリア・ニュージーランドは「安くて安全」であった。
魚介類の購入状況は、「主に国産品を購入した」が62.4%、「国産品しか購入しなかった」が10.2%、「主に輸入品しか購入しなかった」が8.4%、「輸入品しか購入しなかった」が0.3%、「購入したものが国産品か輸入品かわからなかった」が14.5%、「購入しなかった」が4.3%。
食品の妥当な価格水準については、消費者は調査対象品目のすべてで値下げを要望していた。国産品の輸入品に対するプレミアムは若干減少。国産品の輸入品に対する価格許容度については、鮮魚では「3割を越えても国産品を選ぶ」が10.9%、「3割高までなら国産品を選ぶ」が4.7%、「2割までなら国産品を選ぶ」が16.0%、「1割までなら国産品を選ぶ」が19.3%、「同じ値段なら国産品を選ぶ」が37.4%「国産へのこだわりはない」が11.7%。
中国からの輸入食品については「安全性に問題」が92.4%と前回調査(平成20年5月調査、90.3%)よりも上昇。消費者のイメージは前回調査と同様に、中国・アジア(中国以外)・アメリカは「安いが安全面に問題」、EU・北欧は「安全だが高い」、オーストラリア・ニュージーランドは「安くて安全」であった。
魚介類の購入状況は、「主に国産品を購入した」が62.4%、「国産品しか購入しなかった」が10.2%、「主に輸入品しか購入しなかった」が8.4%、「輸入品しか購入しなかった」が0.3%、「購入したものが国産品か輸入品かわからなかった」が14.5%、「購入しなかった」が4.3%。
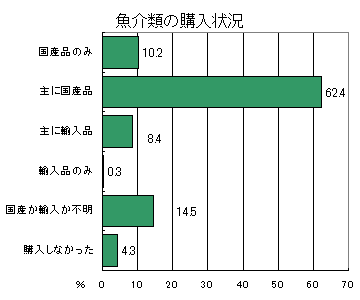 輸入の魚介類を購入した理由は、「安いから」が74.2%、「おいしいから」が30.2%、「国産品がなかったから」が11.5%、「安全だから」が6.0%、「色・形がよかったから」が3.8%、「その他」も3.8%だった。
食肉・野菜・魚介類・果実の生鮮食品4品目全てにおいて、消費者の7割が価格が下がれば「国産品の価格が下がれば購入を増やしたい」と回答した。
米の消費については一年前と比べて6割がかわらないものの、減ったが11.4%に比べ、増えたが25.9%と増加。朝食はご飯中心とパン類中心が4割づつだが、夕食は9割がご飯中心であった。
輸入の魚介類を購入した理由は、「安いから」が74.2%、「おいしいから」が30.2%、「国産品がなかったから」が11.5%、「安全だから」が6.0%、「色・形がよかったから」が3.8%、「その他」も3.8%だった。
食肉・野菜・魚介類・果実の生鮮食品4品目全てにおいて、消費者の7割が価格が下がれば「国産品の価格が下がれば購入を増やしたい」と回答した。
米の消費については一年前と比べて6割がかわらないものの、減ったが11.4%に比べ、増えたが25.9%と増加。朝食はご飯中心とパン類中心が4割づつだが、夕食は9割がご飯中心であった。