トピックス
マサバ07年級は卓越年級と確認
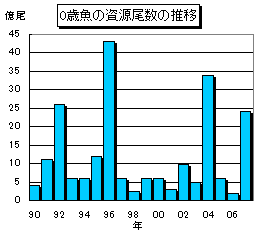 水産庁は、18日、マサバ太平洋系群の再資源評価を行ったところ、2007年級群は他の年級群に比べて加入尾数が特に大きい「卓越年級群」であることが確認されたと発表した。規模としては1996年(43億尾)、2004年(37億尾)、1992年(28億尾)に次ぐもの(24億尾)と見積もられ、加入尾数が20億尾を越えたのは1990年以降ではこの4例のみ。
マサバ太平洋系群については、漁獲可能量(TAC)の管理と併せて2003年から資源回復計画を策定し、大中型旋網の休漁(常磐〜三陸で一帯で2千トン以上の漁獲があった翌日を休漁とする等)により04年卓越年級群の漁獲抑制を行ったところ、04年級群については「取り残し効果」により昨年の3歳魚の時点での資源量(生残量)が92年級群・96年級群(この時は0〜1歳での漁獲が多く、再生産につながらなかった)と比べ3倍程度と、1990年以降では06年に次ぐ第2位の高水準の親魚量となった。
07年級群発生時の環境条件は他の卓越年級群発生時よりも良くなかったものの、親魚量が高い水準であったことが卓越年級群の発生につながったものとみられる。水産庁は近年のサバの好漁は卓越した04年級群の漁獲が中心となっていたことによるが、現在の漁獲の主体は07年級群にとって代わろうとしていることから、07年級群をできるだけ親魚にして親魚資源量を底上げして、資源の着実な回復を図るように努めていくとしている。
なお、14日に開催された水産政策審議会資源管理分科会で2008年漁期のサバ類の漁獲可能量(TAC)の期中改訂が行われ、14万9千トン増枠とそれに伴う大臣管理分・知事管理分の追加配分が承認された。2008年漁期のサバ類の漁獲可能量(TAC)は昨年11月に61万5千トンと設定されたが、最新の資源評価も踏まえ、調整枠を含めた総漁獲可能量を76万5千トンに改め、大臣管理分は6万1千トンの増枠で30万1千トンとなった。
水産庁は、18日、マサバ太平洋系群の再資源評価を行ったところ、2007年級群は他の年級群に比べて加入尾数が特に大きい「卓越年級群」であることが確認されたと発表した。規模としては1996年(43億尾)、2004年(37億尾)、1992年(28億尾)に次ぐもの(24億尾)と見積もられ、加入尾数が20億尾を越えたのは1990年以降ではこの4例のみ。
マサバ太平洋系群については、漁獲可能量(TAC)の管理と併せて2003年から資源回復計画を策定し、大中型旋網の休漁(常磐〜三陸で一帯で2千トン以上の漁獲があった翌日を休漁とする等)により04年卓越年級群の漁獲抑制を行ったところ、04年級群については「取り残し効果」により昨年の3歳魚の時点での資源量(生残量)が92年級群・96年級群(この時は0〜1歳での漁獲が多く、再生産につながらなかった)と比べ3倍程度と、1990年以降では06年に次ぐ第2位の高水準の親魚量となった。
07年級群発生時の環境条件は他の卓越年級群発生時よりも良くなかったものの、親魚量が高い水準であったことが卓越年級群の発生につながったものとみられる。水産庁は近年のサバの好漁は卓越した04年級群の漁獲が中心となっていたことによるが、現在の漁獲の主体は07年級群にとって代わろうとしていることから、07年級群をできるだけ親魚にして親魚資源量を底上げして、資源の着実な回復を図るように努めていくとしている。
なお、14日に開催された水産政策審議会資源管理分科会で2008年漁期のサバ類の漁獲可能量(TAC)の期中改訂が行われ、14万9千トン増枠とそれに伴う大臣管理分・知事管理分の追加配分が承認された。2008年漁期のサバ類の漁獲可能量(TAC)は昨年11月に61万5千トンと設定されたが、最新の資源評価も踏まえ、調整枠を含めた総漁獲可能量を76万5千トンに改め、大臣管理分は6万1千トンの増枠で30万1千トンとなった。