トピックス
道内秋サケ、低調のまま終漁へ
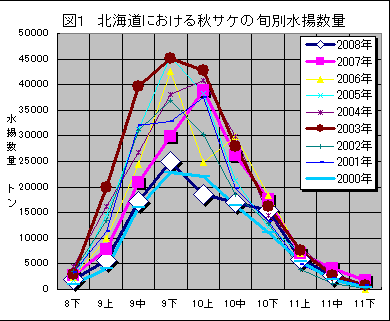 北海道の秋サケ定置網漁は、例年通り8月下旬に帯広〜釧路地区で、続いて根室地区でスタートした。9月に入るとオホーツク海側・日本海側・日高地区等でも始まり、全道で操業が本格化した。例年だと水揚げのピークは9月下旬から、遅い年でも10月上旬に迎えるが、今年は大きな盛り上がりのないまま、漁期終盤を迎えている(図1参照)。
シロサケは春鮭鱒漁で春〜初夏に沖で漁獲されたものは「トキサケ、時知不(トキシラズ)」と呼ばれ、身に脂がある。秋になると産卵の為に『母川回帰』して産まれた川(必ずしもそうと限らないようだが・・・)の近くに戻って来るが、川を遡上する前に河口の近くに張られた定置網で漁獲される。これが「秋サケ、秋味」と呼ばれ、身の栄養分が筋子(卵巣)や白子(精巣)の発達に使われる。マスコミによく登場するケイジ(鮭児)は同じシロサケでもロシア・アムール系で、卵巣・精巣が未成熟で、身に脂があるのが特徴で、たまたまアムルール川に帰る途中に日本系の群れに混じって道東の羅臼等の定置網にかかり、キロ3万円前後もする。日本のシロサケのふ化放流事業は明治時代から100年に渡る長い歴史があり、近年回帰率の向上とともに成果が現れている。しかし、今年は2005年にふ化放流した稚魚の生き残りが悪く、今年の不漁につながっているようだ。
北海道の秋サケ定置網漁は、例年通り8月下旬に帯広〜釧路地区で、続いて根室地区でスタートした。9月に入るとオホーツク海側・日本海側・日高地区等でも始まり、全道で操業が本格化した。例年だと水揚げのピークは9月下旬から、遅い年でも10月上旬に迎えるが、今年は大きな盛り上がりのないまま、漁期終盤を迎えている(図1参照)。
シロサケは春鮭鱒漁で春〜初夏に沖で漁獲されたものは「トキサケ、時知不(トキシラズ)」と呼ばれ、身に脂がある。秋になると産卵の為に『母川回帰』して産まれた川(必ずしもそうと限らないようだが・・・)の近くに戻って来るが、川を遡上する前に河口の近くに張られた定置網で漁獲される。これが「秋サケ、秋味」と呼ばれ、身の栄養分が筋子(卵巣)や白子(精巣)の発達に使われる。マスコミによく登場するケイジ(鮭児)は同じシロサケでもロシア・アムール系で、卵巣・精巣が未成熟で、身に脂があるのが特徴で、たまたまアムルール川に帰る途中に日本系の群れに混じって道東の羅臼等の定置網にかかり、キロ3万円前後もする。日本のシロサケのふ化放流事業は明治時代から100年に渡る長い歴史があり、近年回帰率の向上とともに成果が現れている。しかし、今年は2005年にふ化放流した稚魚の生き残りが悪く、今年の不漁につながっているようだ。
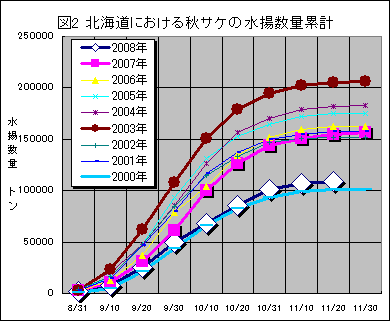 採卵するためのふ化放流用親魚が充分確保できていないことから、10月中には根室地区では定置網の一部を揚げて数日間休漁を行ったほか、特に低調だった日本海側では漁期終盤まで休漁を行い、そのまま終漁した。今年は10月下旬にようやく10万トンを超え、過去最高であった2003年の20万6千トンの半分の水準で、昨年の15万7千トンよりも3割少ない。2000年は10万1千トンと近年では最も少なく、今年はこの年よりやや多い11万トンとなる見込みだ(図2参照)。
採卵するためのふ化放流用親魚が充分確保できていないことから、10月中には根室地区では定置網の一部を揚げて数日間休漁を行ったほか、特に低調だった日本海側では漁期終盤まで休漁を行い、そのまま終漁した。今年は10月下旬にようやく10万トンを超え、過去最高であった2003年の20万6千トンの半分の水準で、昨年の15万7千トンよりも3割少ない。2000年は10万1千トンと近年では最も少なく、今年はこの年よりやや多い11万トンとなる見込みだ(図2参照)。
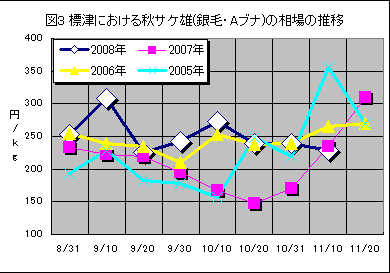 産地価格をみてみると指標とする標津の雄(銀毛・Aブナ)では250〜300円/kgで、昨年の10月上〜中旬と比べると100円近く高く、ここ2〜3年浜値を支えた輸出もサンマやサバ同様に円高・ドル安・ユーロ安で鈍化したとされる(図3参照)。
産地価格をみてみると指標とする標津の雄(銀毛・Aブナ)では250〜300円/kgで、昨年の10月上〜中旬と比べると100円近く高く、ここ2〜3年浜値を支えた輸出もサンマやサバ同様に円高・ドル安・ユーロ安で鈍化したとされる(図3参照)。
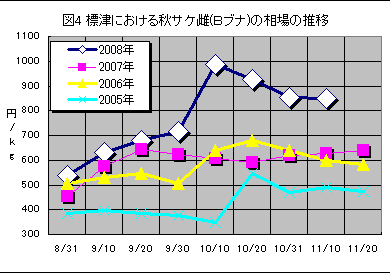 一方、標津の雌(Bブナ)では不漁が決定的となった10月10日前後には高値でキロ1千円をつけ、15日には羅臼で雌BCが高値で1千円を突破。数量は少ないものの、函館では10月中旬以降、高値が1千円〜1千200円で推移した。北海道各地の雌では10月中旬は900円台の展開で、10月下旬以降はやや下げた800円台となっている(図4参照)。
秋サケの雌は身よりも卵に価値があり、雄よりも高い価格で取り引きされる。イクラは筋子をほぐして醤油漬けや塩漬けにして作る。北海道の加工業者はイクラを作る業者も多いが、今年のように原料高だと正月の最需要期を前に価格を上げたくとも、消費が低迷しているとなかなか製品に価格を転嫁しにくい状況だ。
一方、標津の雌(Bブナ)では不漁が決定的となった10月10日前後には高値でキロ1千円をつけ、15日には羅臼で雌BCが高値で1千円を突破。数量は少ないものの、函館では10月中旬以降、高値が1千円〜1千200円で推移した。北海道各地の雌では10月中旬は900円台の展開で、10月下旬以降はやや下げた800円台となっている(図4参照)。
秋サケの雌は身よりも卵に価値があり、雄よりも高い価格で取り引きされる。イクラは筋子をほぐして醤油漬けや塩漬けにして作る。北海道の加工業者はイクラを作る業者も多いが、今年のように原料高だと正月の最需要期を前に価格を上げたくとも、消費が低迷しているとなかなか製品に価格を転嫁しにくい状況だ。