トピックス
グリーンピースが海洋シンポ開催
NGOグリーンピース・ジャパンの主催で国際海洋環境シンポジウム「海から魚がいなくなる? 私たちが今できること」が、国連大学ウ・タント国際会議場(東京都渋谷区)で開催し、200人以上が参加。国内外の海洋・水産の研究者の基調講演、漁業者・流通業者や行政担当者等の事例報告に続き、パネルディスカッションが行われ、今日の漁業・水産業を取り巻く問題点や対応策について活発な議論が行われた。
ダニエル・ポーリー コロンビア大学漁業センター所長は、漁獲量の減少は過剰漁獲が原因とし、漁業資源減少の解決策として海洋保護区の設置の重要性を訴えた。また、「現在の漁業における持続可能性の欠如は、主に小規模漁業を駆逐する大規模漁業の過剰な漁獲能力にある」とし、「小規模漁業は大規模漁業に比べ雇用も多く、燃料に対する漁獲量も多く、投棄魚も少ないので、優遇する措置を導入することが必要」と問題点を指摘した。
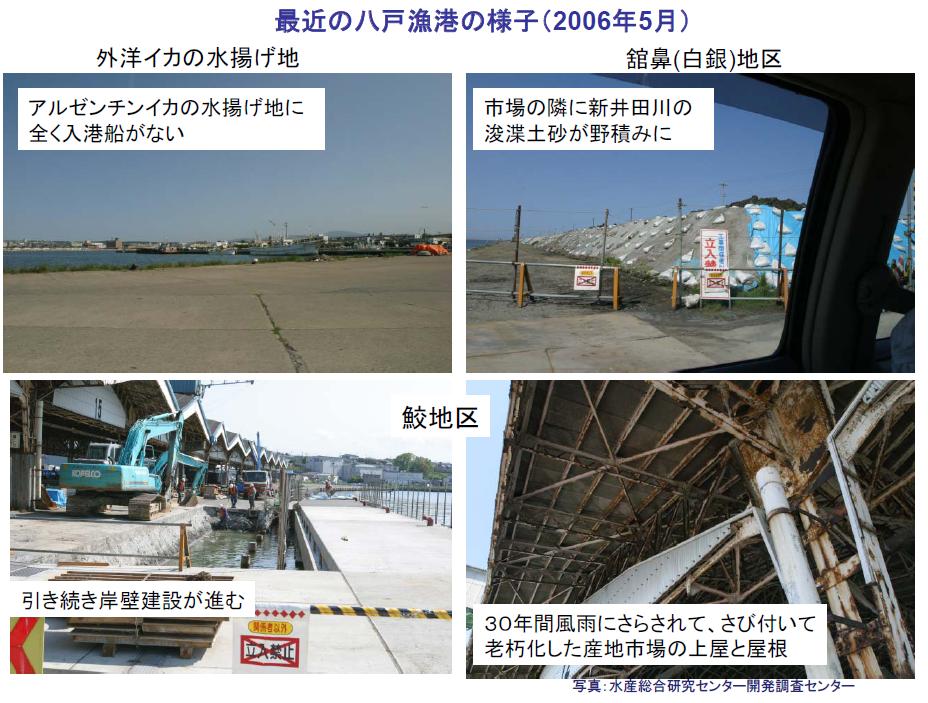 政策研究大学院大学の小松正之教授(元水産庁漁場資源課長)は日本の水産業の未来に向けて、乱獲から脱却して資源の持続的利用を図る上で、オリンピック制から排他的漁獲の永続性と価値が保証される個別譲渡制割当(ITQ)の導入、過剰漁獲能力の削減をするために減船への財政支援、無駄な投資とコストを削減して利益を上げるようにすることが必要性を訴えた。
政策研究大学院大学の小松正之教授(元水産庁漁場資源課長)は日本の水産業の未来に向けて、乱獲から脱却して資源の持続的利用を図る上で、オリンピック制から排他的漁獲の永続性と価値が保証される個別譲渡制割当(ITQ)の導入、過剰漁獲能力の削減をするために減船への財政支援、無駄な投資とコストを削減して利益を上げるようにすることが必要性を訴えた。
 山口県見島のマグロ一本釣り漁師の佐々木敦司氏は「境港のまぐろ漁業の現実」と題した事例報告を行った。佐々木氏は見島沖で最初にクロマグロ一本釣り漁を起こした人。まき網による日本海のクロマグロ漁は6月から操業を行って7月中〜下旬に産卵を行う前に大量に漁獲してしまうこと、まき網の漁獲するサイズが年々に小さくなっており30kg台の一回も産卵しないサイズの小型魚まで大量に漁獲していることを指摘。一本釣りで釣れるのも250kg以上の大型魚のみで、以前釣れたような小〜中型魚がいなくなるとともに年々釣れる本数も減っており、あと2〜3年で日本海のクロマグロ資源は潰れると警鐘をならす。国に訴えてもだめで、研究者も学会向けの研究のみで、研究者に協力しても漁業者に全く還元されていないという。
山口県見島のマグロ一本釣り漁師の佐々木敦司氏は「境港のまぐろ漁業の現実」と題した事例報告を行った。佐々木氏は見島沖で最初にクロマグロ一本釣り漁を起こした人。まき網による日本海のクロマグロ漁は6月から操業を行って7月中〜下旬に産卵を行う前に大量に漁獲してしまうこと、まき網の漁獲するサイズが年々に小さくなっており30kg台の一回も産卵しないサイズの小型魚まで大量に漁獲していることを指摘。一本釣りで釣れるのも250kg以上の大型魚のみで、以前釣れたような小〜中型魚がいなくなるとともに年々釣れる本数も減っており、あと2〜3年で日本海のクロマグロ資源は潰れると警鐘をならす。国に訴えてもだめで、研究者も学会向けの研究のみで、研究者に協力しても漁業者に全く還元されていないという。
流通業者からの事例報告として、築地の仲卸の(株)亀和商店代表取締役社長の和田一彦氏は、水産のエコラベルとして世界的に広まっているMSC(海洋管理協議会)の流通・加工課程の認証であるCoC認証の取得の経緯を紹介。小売業からはイオントップバリュ株式会社・トップバリュ商品本部生鮮食品部部長の山本泰幸氏も、MSC取得商品の販売の実情を紹介。山本氏は消費者のMSCの認識率は10%以下で、MSCの経費は価格に転嫁できていないのが実情。 グリーンピース・ジャパンの花岡和佳男氏が海洋保護区の設置例を紹介するとともに海洋資源の回復に保護区の重要性を訴えた。 発表の要旨はこちらをご覧下さい。(PDFファイル)