トピックス
シーフードショー
 『シーフードショー』も最終日を迎えました。今年から新たに導入された、一般消費者を対象にした「おさかなモニター」での来場者も多く、夏休みということもあり、親子連れも多数みられました。女性の年輩のグループは、「食べ放題みたい」とあちらこちらで試食を楽しんでいました。
セミナーやシンポジウムは5会場に別れ、1日に11〜17演題行われ、どの会場も盛況でした。その中から概略をいくつか掲載します。
『シーフードショー』も最終日を迎えました。今年から新たに導入された、一般消費者を対象にした「おさかなモニター」での来場者も多く、夏休みということもあり、親子連れも多数みられました。女性の年輩のグループは、「食べ放題みたい」とあちらこちらで試食を楽しんでいました。
セミナーやシンポジウムは5会場に別れ、1日に11〜17演題行われ、どの会場も盛況でした。その中から概略をいくつか掲載します。
 水産ブランド戦略〜水産物をブランド化するためのヒント〜
水産ブランド戦略〜水産物をブランド化するためのヒント〜
(株)ブランド総合研究所 代表取締役社長 田中章雄氏
究極のこだわり商品が大ブームになっている。徳島の「ももいちご」は16粒で1万6千円。「ルセット」のパンは1斤4,900円。「関アジ・関サバ」は2尾で7,700円。「紀州五代梅」1粒3,150円。「おみたまプリン」2個1万円。
「ももいちご」は1つの苗に20の花がなるが、花をとって4〜5つにし、徹底的に大きくする。大きくなると自分の重さで潰れ、地面に付くと腐ってしますので、簀の子にのせて回転させながら育てる。生産しているのは36農家のみで、1農家あたりの生産する量も限定。出荷はスケジュールで順番をずらしながら、流通量も多くならないようにしている。出荷は大阪の1社のみ。
ルセットの食パンは、天然酵母を使用しており、天然酵母に合う原料を探して使用。ルセットは幻のパンで、廃校なった教室を利用した池尻の世田谷のものづくり学校で作っている。買いたくても買えない商品。従来は1ヶ月前に予約して、抽選を行っていた。現在は、半年で2万3千円の会費を払って頒布会に加入すると毎月1回必ず買える。
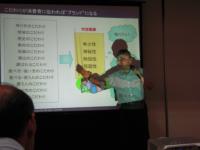 紀州五代梅は1粒3,150円する。賞味期限は60年。還暦や新築のお祝いに送る人が多い。昔の梅干しは塩分20%だったが低塩指向が進み、平均は7〜8%だが、少ない物は3%。塩分が少ないと保存性が低下するので、最近は抗菌性のあるハチミツ等を添加する。1粒200〜300円台の商品は人気がある。
茨城の小美玉市は、元々、鶏卵の産地で10個1パックのブロイラーの卵を150円程度で、東京を中心に出荷していた。卵を使った原料を厳選した商品を開発することになった。プッチンプリンは2個98円。コンビニの高いプリンでも1個150円。希少な初生卵のみ使用。小さいが旨味や栄養分が濃く、味も濃厚。東京麻布のフランス料理店のパティシエが作り、器も天心焼きを使用。
紀州五代梅は1粒3,150円する。賞味期限は60年。還暦や新築のお祝いに送る人が多い。昔の梅干しは塩分20%だったが低塩指向が進み、平均は7〜8%だが、少ない物は3%。塩分が少ないと保存性が低下するので、最近は抗菌性のあるハチミツ等を添加する。1粒200〜300円台の商品は人気がある。
茨城の小美玉市は、元々、鶏卵の産地で10個1パックのブロイラーの卵を150円程度で、東京を中心に出荷していた。卵を使った原料を厳選した商品を開発することになった。プッチンプリンは2個98円。コンビニの高いプリンでも1個150円。希少な初生卵のみ使用。小さいが旨味や栄養分が濃く、味も濃厚。東京麻布のフランス料理店のパティシエが作り、器も天心焼きを使用。
高くても売れる理由は、こだわりが消費者に伝わればブランドになり、値引きしなくても売れる。「こだわり」は演出や歴史、「付加価値」は希少性や物語等を加味することで、消費者がその商品を知りたい、食べたい、伝えたいという方向に向く。「こだわり」をいかに作って消費者に伝えるかが重要。
もくもく手作りファームは農業公園で、13人で会社を作った。現在、年間50万人の来場者がある。もとは農場で伊賀健豚という豚を飼育していた。今でこそブランド豚がでているが、当時は豚の味は一般消費者には評価されにくかった。バイヤーは美味しい物は扱わず、売れる商品を扱うことから、付加価値を付けるために作った伊賀健豚で作ったハムは高く売れなかった。また、豚の産地イメージも三重県よりも自然が売りになる北海道の方が一般的に強い。
手作り体験教室を開催し、6家族が最初に参加。ウインナーを作った。翌日、参加者から子供が食べたいといっているので、送って欲しいという電話があった。その後、通信販売を開始した。子供がもくもくのソーセージを食べると、現地でソーセージを作った体験を思いだし、話が盛り上がる。
商品には美味しいと書いてあるがあまり信じず、人から美味しいと言われると信じるもの。最初は製品を作ること・売ることしか考えていなかったが、消費者の満足する方向へと気づき、農場を占めて、体験型施設に転換した。社員は13人から300人に増え、平均年齢も27歳と若い。
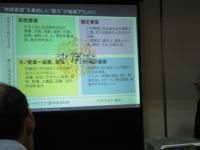 ブランド化のポイントは、究極の商品(品質・鮮度)を作ること。加工品を作ること(出荷調整が利く)。地域のイメージや資源を活用する(観光セリの実施)情報をしっかり発進することなど。
ブランド化のための管理は大切で、「ももいちご」は3月以降品質低下するので「ももいちご」としては出荷しない。原産地や品質の保証。顧客の満足度の管理。偽物の排除も必要。
ブランドとは。商品と組織に対する、消費者からの評価と期待であると締めくくった。
ブランド化のポイントは、究極の商品(品質・鮮度)を作ること。加工品を作ること(出荷調整が利く)。地域のイメージや資源を活用する(観光セリの実施)情報をしっかり発進することなど。
ブランド化のための管理は大切で、「ももいちご」は3月以降品質低下するので「ももいちご」としては出荷しない。原産地や品質の保証。顧客の満足度の管理。偽物の排除も必要。
ブランドとは。商品と組織に対する、消費者からの評価と期待であると締めくくった。