トピックス
冷凍まぐろ類の相場続伸
燃油高騰により採算割れするということで台湾の遠洋まぐろ延縄船の休漁に引き続き、日本の遠洋まぐろ延縄船の休漁を行うと一般のマスコミ報道でもされた。台湾・日本とも2割の船が休漁する予定だったが、台湾船は半分休むとの報道もある。今後、冷凍まぐろ類の供給が減るのは確実だ。ここのところ、築地市場の冷凍まぐろ類の相場は日に日に上げている。 冷凍メバチは4月上旬までは平均キロ800円だったが、最近は950円まで上げた。一方、冷凍キハダは4月上旬までは平均キロ620〜630円だったが、最近は800円まで上げている。前回は2006年3月に台湾船の大幅減船が報道され、供給の先細り感以上にマスコミの過熱報道があり、マスコミが「マグロが食べられなくなる、マグロが食べられなくなる」と煽りすぎた結果、相場を上げすぎて消費者がついて来れず、逆に冷凍まぐろ類の売れ行き不振を招き、逆に相場を元に戻してしまった経緯がある。遠洋まぐろ延縄船の場合、10年近く前は1日の採算ラインが120〜130万円だったのが、マルシップや研修生の制度でインドネシア人を乗せて人件費を抑えることで、1日の採算ラインは半分まで落とすことができた。しかし、末端消費者のまぐろに対するニーズは赤身ではなく、安いトロである養殖の脂物に移っている。だから大手水産会社も儲かるマグロ養殖に手を出している。国内の冷凍メバチ・冷凍キハダのマーケットは萎んでしまったので売り先がなく、現状では十分に利益がでる状況ではなく、業界団体の日かつ漁協も活路を輸出して海外のマーケットを見いだそうとしていた。
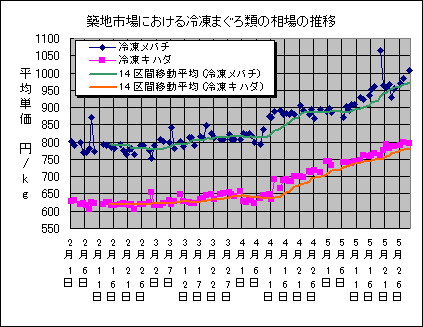 今回の燃油高騰により燃油が1日操業すると10万円余計にかかり、その分まで魚価に反映できている訳ではない。大西洋のクロマグロや南半球に生息するミナミマグロといった天然の高級マグロが獲れる漁場は資源悪化もあり、日本船はどんどん閉め出され、結局は赤身が獲れる漁場しか残されていないのが現状だ。今回大規模に休むことで、資源回復や魚価の回復といった意味もあるだろう。マグロ業界にとって大きな転換期になりそうだ。
今回の燃油高騰により燃油が1日操業すると10万円余計にかかり、その分まで魚価に反映できている訳ではない。大西洋のクロマグロや南半球に生息するミナミマグロといった天然の高級マグロが獲れる漁場は資源悪化もあり、日本船はどんどん閉め出され、結局は赤身が獲れる漁場しか残されていないのが現状だ。今回大規模に休むことで、資源回復や魚価の回復といった意味もあるだろう。マグロ業界にとって大きな転換期になりそうだ。