2003年サンマ
単位:数量,1000トン、価格,円/kg
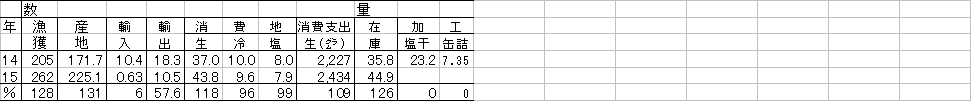
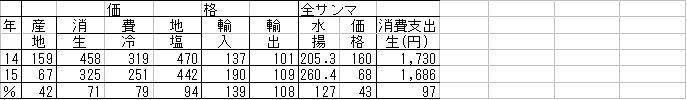
資源と漁獲量
サンマの資源量は、1980年代後半〜1990年代中期は良好な資源状態を保っていたが、1998・1999年以降急激に資源水準が低下した後、2000年以降緩やかに回復傾向にあった。そして2003年の調査では沿岸域の資源水準は高く、沖合域にも膨大な未利用資源があることから、資源水準は高かったと判断されている。
15年の漁獲量は前年を上回る約27万トン弱であったとみられる。
また、本年は漁獲量の増加が当初より顕著で,9月に入って直ぐに休漁措置が講じられたのを始め、その後も積荷制限も含め漁期終了まで恒常的に休漁措置が講じられた。
本年は漁期当初の7月8日から10トン未満船の流し刺網、同19日には5トン未満船の棒受網、26日には10トン未満の棒受網の操業が開始された。そして棒受網の20トン未満船が8月8日、同40トン未満船が8月13日、同40トン以上船が8月18日解禁となった。
本年のスタート時の漁は近年では低かった2002年の1078トンの約2倍に当たる2000トン弱の水揚げであった。その後8月以降、そして大型船が出漁した8月下旬に入って漁況はやや上向いたが、好漁が長続きせず前年をやや上回る程度であった。9月の盛漁期に入って漁況は好調となり、はっきりと前年を上回り、魚価の低落も顕著になった。10月中旬以降ようやく休漁措置もあり、前年をやや下回る水揚げもあったが、今度は本州で11月以降もまとまった漁獲が続き水揚げを伸ばした。そして最終的には12月15日をもって終漁した。
本年の初期漁場は昨年と違い釧路南東沖合から始まる展開で、その後のやや東寄り沿岸に移動し、8月に入って道東沖合と一部納沙布沿岸、大型船が出漁した以降の8月下旬には再度道東沖合の親潮第2分枝の先端に形成された。
9月上旬には昨年より1月早く初めて三陸の黒崎沖(直ぐに消滅)にも漁場が形成され、道東沖一帯と両方に分かれた。9月中旬には襟裳岬東沖にも漁場が形成されたが、このころから道東漁場は日変化もみられたが9月一杯は道東沖が主漁場であった。10月に入ってからは黒埼、魹埼沖が主漁場に変わり、中旬には金華山沖、下旬には常磐沖、犬吠崎沿岸にも漁場が形成された。そして10月後半からは犬吠埼沿岸と道東沖合の2箇所(11月中旬で終了)に漁場形成がみられた。なお、本年もオホーツクでは、10月中旬に僅か12トン程度の水揚量で昨年(9トン)並みの低調さであった。
魚体は、本年は予報とおり昨年に比べると当初から体重、体長とも大きく、7月は大型29-31cmの110-160g主体、8月は30-31cmの140-160g主体で、9月に入ってからは30-31cm―160g主体に中型も混じり始め、その後小型も混じるようになった。大型船が出漁した8月下旬頃から9月まで大型の割合が急増したが、その後は中型主体に変わり、10月以降は中型魚(26-28cm)の出現割合が増え、通算では大型82%(37%)、中型16%(51%)、小型2%(12%)であった。
また本年は漁期当初から大型魚が多く漁期後半まで続き、鮮魚向けに集中したため、需要を越えた供給結果となり魚価急落の一因になった。
魚価は、当初から在庫が多かったこともあり、初漁期は前年以上に極端な高値にはならず、しかも大型船が出漁し,寄港が始まった8月下旬には既に2桁台に急落した。そして、一時やや戻したものの水揚げが集中する9月に入った途端2桁台に再暴落し、その後は漁期終了まで2桁台の日が続いた。その結果、通算も67円で前年の159円の半値以下まで下げ、来期の漁自体まで影響しそうな価格帯となった。
在 庫 量
本年は昨年の5.9万トンより少ない5万トンの越年在庫から始まったが、前年搬入された輸入物も多く、新漁前の6,7月には前年を上回る水準となった。そして例年在庫が最も少なくなる8月には前年より約7千トン以上も多い高水準の在庫となった。しかも大型船が出漁したころから漁獲も好転し、9月から在庫は大幅な増加傾向に転じた。しかも魚体も大型に偏ったことでそれ以降も在庫は増加するのみで価格の急落もみられた。その結果特に下半期の高在庫傾向は極端になり、越年在庫も7.5万トンと前年(5万トン)を大幅に上回り、前々年(5.9万トン)をも大きく上回り近年でも高水準であった。
平均在庫量は、昨年以上に多く、4.5万トンで多かったほぼ前年(3.6万トン)を大きく上回り、近年でも最高に水準となった。
消費地入荷量と価格
15年の消費地入荷量(10大都市)は、5.4万トン(生4.4万トン、冷1万トン)と生主体にほぼ前年(4.7万トン、生3.7万トン、冷1万トン)並みで多かった。
本年は、上半期の消費地への入荷量も極端に多くはなかったが、下半期特に全船が出揃った8月以降の多さ、特に9〜11月には近年では、極めて多い水準であった。
本年は産地での魚体が大きく、40尾、45尾サイズ主体で前年(40尾、45尾、50尾主体)より大きかった。
また、本年の塩干物の入荷は0.8万トンで引続き前年(0.8万トン)並みであった。
本年の価格のピークは7、8月にみられたが、その後例年同様入荷のピークを迎える9月に入って急落した。そして、10月以降は9月並みの価格で推移したが、昨年以上に低水準が顕著であった。
平均価格は生325円(前年458円)、冷251円(前年319円)、塩442円(前年470円)で、生鮮、冷凍、塩干何れも下げたが、これは特に鮮魚向けの入荷が極端に多かったこともあって、冷凍、塩蔵ともこれに押され気味であり、出番を失ったことの結果である。また消費支出(1世帯当たり)をみると、数量ベースではかなり上回り、本年の産地水揚げに比例して末端での購買量も多く単価も安かった、ことがわかる。
輸 出 入
本年の輸入は、631トンで前年(10,429トン)を大幅に下回った。
これは前年の輸入量(加工向け主体)が多かったことと、今漁期の漁が極めて好調に推移したこともあって、本年は極めて少量であった。
輸出はH4年をピークに近年減少傾向が続いているが、本年も1.1万トンと前年(1.8万トン)を下回った。
価格も、輸入190円(前年137円)、輸出109円(前年101円)であった。
本年は輸出、輸入とも極めて低調な年であった。
本年の輸出は、中国向けが遂に最も多くなり次にフィジー、続いてトリニダッドドバコ、サモア、米国、台湾の順となり韓国向けは僅かであった。