03年マアジ
単位:数量、1000トン、価格、円/kg 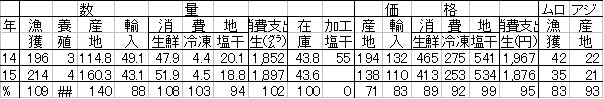 漁獲量と資源
漁獲量と資源
15年の漁獲量は20万トンを越え、前年をやや上回る水準であったが、近年ではやや低い水準の漁獲量に終わった。
本年は主体の東シナ海及び、山陰海域でも昨年とは反対にやや好調な漁獲であり、水揚げも昨年を上回った。
主力の東シナ海及び日本海沿岸で主に漁獲される対馬暖流系群の資源量は、1980年代以降増加傾向を示し、1990年代の中盤は高い水準を維持した。しかし99年以降はそれよりやや低くなり現在に至っており,現在の水準としては中位といわれている。
また太平洋系群は1982年以降一貫して増大、特に1990年代中ごろ高く安定していた。しかし加入量の減少により1997年以降資源量は減少に向かった。しかし、再度2001年には加入量の増大がみられたものの、2002年には加入量が減少している。現在資源状況は中水準で減少傾向にある。
以上のように何れも資源水準は中位であるが、親魚量の増加確保は、資源の安定的確保には極めて重要であるとともに、また当歳魚の漁獲の減少があれば、漁獲量の増加が期待できるとされている。
ムロアジ類
本年のムロアジは、前年より再度漁獲が下回り資源状況の回復はみられておらず、周年を通じてやや低調な漁獲にとどまっている。
(近年MAX:H2年 10.9万トン)
産地水揚量と価格(51港)
海域別水揚量 月別漁獲量 月別価格推移
15年のマアジの水揚量は、17.2万トンで前年(12.6万トン)をかなり上回った。
九州西方海域では、春の盛漁期(4〜6月)に昨年とは違い漁獲が伸びた。また、秋口の9,10月には昨年同様当歳魚の大きな漁獲の伸びがみられたこともあり、水揚げは前年をかなり上回った。
また、山陰沿岸では九州同様、秋口9〜10月主体に下半期に年間の7割以上の漁獲であり、昨年を大幅に上回る水揚げであった。したがって、総漁獲量でも東シナ海にかなり近づいた1年となった。
太平洋側では昨年に続き薩南海域を始め、やや低調で昨年を下回った。
魚体は、東シナ海では100g以下のアジが44%(前年39%)(70g以下の豆アジは全体の31%前年19%)を占め主体であり、本年も魚体の小型化傾向が特に顕著であった。
山陰沿岸でも、依然、魚体の大きいマアジは少なく豆アジ(0〜1歳魚)主体で、依然型の良いアジは僅かであった。
価格は、138円で水揚げの増加を反映し前年(194円)をかなり下回ったが、秋口の当歳魚の好漁獲を反映した結果でもある。
輸 入
15年のアジの輸入は、4.3万トンで5〜7万トンの近年の範囲内では低水準であり、前年(4.8万トン)を引続き下回り、2年続けての低水準にとどまった。
本年は、オランダ1.3万トン(前年: 1.6万トン)、ノルウェー0.8万トン(前年:0.8万トン、アイルランド0.8万トン(前年0.8万トン)でオランダの減少、ノルウェー、アイルランドともにやや停滞気味であった。韓国は0.3万トンで前年(0.6万トン)をやや下回ったが、本年はNZが0.4万トンと比較的多かった。
本年は、国内漁がやや好調であったことも反映してか、主に大西洋側からの輸入が減少した。
価格は、110円で前年(132円)を下回ったが、開き塩干アジの需要減少も影響している可能性もある。
在 庫 量
本年の在庫量は、4.4万トンとほぼ前年(4.4万トン)並みであった。
これは、国内生産量の増加、輸入量の減少が相殺した結果によるものである。
消費地入荷量と価格
15年の消費地入荷量(10大都市)は、5.7万トン(生5.2万トン、冷0.5万トン)で産地での水揚げ増加を反映して前年5.2万トン(生4.8万トン、冷0.4万トン)を上回った。なお、塩干のみは1.9万トンで前年(2万トン)をやや下回り引続き漸減傾向が続いている。
本年の1世帯あたりの消費支出は数量では前年を上回ったものの、金額ではやや減少しており、単価的には産地・消費地での下落傾向が反映した格好となった。
価格は、生413円(前年465円)、冷253円(前年275円)、塩干534円(前年541円)であったが、生鮮、冷凍、塩干とも下落傾向が顕著であった。