02年 サンマ
単位:数量,1000トン、価格,円/kg
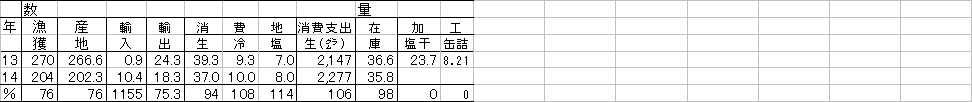
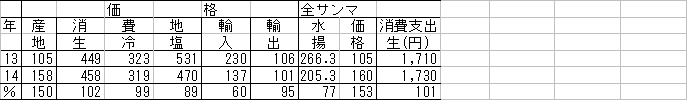
資源と漁獲量
近年サンマの資源量は、1995〜1997年にかけてほぼ200万トン強で安定していた。しかし1998・1999年以降急激に減少がみられたが、2000年,2001年とも漁獲量が回復した。しかし資源水準が高かった90年代中期には及ばないといわれている。またサンマ資源は30年程度の周期で大きな資源変動があるといわれている。資源の長期変動傾向からみて現在は1980年代から続いた資源の高水準安定期から資源水準が低下する時期に入っており、より漁獲変動の激しい不安定な時期とみられている。
14年の漁獲量は前年を下回る約20万トン強であったとみられる。
また,本年は漁獲量が減少したこともあって,前年程の休漁措置はみられなかったが10月の中旬に1回休漁措置が講じられた。
本年は漁期当初の7月8日から10トン未満船の流し刺網、同19日には5トン未満船の棒受網、26日には10トン未満の棒受網の操業が開始された。本年は近年では高かった2001年とはやや様相が違い、前年の約半分に当たる1078トンの水揚げに終わった。その後8月以降、そして大型船が出漁した8月下旬に入って漁況はやや上向いたが、好漁が長続きせず前年を下回って推移した。9月の盛漁期に入って漁況は好調となったが、中旬を除いてこれも前年の域まで達せず、低調であった。10月中旬以降前年を上回る時もあったが北海道は11月頭で終わり、本州も総じて低調のまま12月中旬をもって終漁した。
漁場も初期は襟裳岬東と落石沖合から始まる異例の展開で、その後の7月下旬以降は道東沖合、そして8月下旬には魚群の南下もあり襟裳岬の南東にも広く形成され、道東近海漁場は10月下旬まで続いた。
10月上旬に初めて三陸黒崎沖にも漁場が形成され、道東近海と両方に分かれたが本年は漁場の北偏傾向が続き10月一杯は道東沖が主漁場であった。さすがに11月に入ってからは三陸南部と常磐沖に主漁場が移ったが常磐沖がより主体であった。また昨年に引続き常磐から犬吠埼近海(前線北側)での本格的な漁場形成がみられた。なお、本年も10月9,10日に水揚げがあったのみで、水揚量は僅か9トン程度で昨年(2,481トン)を更に下回った。
魚体は、本年は昨年に比べると当初から体重、体調とも小さく、7月は大型でも1,2cm小さく、8月は中型主体で、大型船が出漁した8月下旬頃から9月まで大型の割合が急増したが、その後は中型主体に変わり、通算では大型37%、中型51%、小型12%であった。
また肥満度は当初は小さかったが、全体を通じると明瞭な差はみられなかったのが特徴であった。
魚価は、当初から在庫が多かったこともあり、初漁期からキロ当たり三桁台の推移で、極端な高値にはならなかった。しかし、その後大型船が出揃った8月以降、漁獲が集中する9月になっても三桁台を維持し、10月上旬までそれが続いた。そして中旬になってようやく二桁台の日もみられたが、概ね高価格帯で推移した。その結果、通算も158円で前年の105円をかなり上回った。
在 庫 量
本年は前年度の好漁を受けて昨年の4.4万トンより多く近年でも最も高い5.9万トンの越年在庫から始まった。この多さは、新漁が始まった7月まで続き前年を上回って推移した。例年在庫が最も少なくなる8月にボトムになったものの水準としては本年も高かった。漁獲が本格化する9月以降、例年通り在庫は増加傾向に転じた。しかし漁の推移もあり前年ほどの急増さはみられなかった。しかし周年を通じて高在庫傾向は変わらず、越年在庫も5万トンと前年(5.9万トン)を下回ったものの、前々年(4.4万トン)を大きく上回り近年でも高水準であった。
平均在庫量は、前年来の在庫の多さもあって本年も多く、3.6万トンで多かったほぼ前年(3.7万トン)並みであった。
消費地入荷量と価格
14年の消費地入荷量(10大都市)は、4.7万トン(生3.7万トン、冷1万トン)と生主体にほぼ前年(4.8万トン、生3.9万トン、冷0.9万トン)並みで多かった。
本年は、当初から在庫が多かった影響を受けて、上半期から消費地への入荷量も昨年、一昨年以上に多かったが、さすがに最需要期の9〜10月には、漁の低迷もあって昨年をやや下回ったが、近年では前年に次ぐ多さであった。
また本年の入荷の主体は40尾、45尾、50尾で大型主体であったが。前年(35尾、40尾、45尾主体)よりややサイズが小さかった。
また、本年の塩干物の入荷は0.8万トンで引続き前年(0.7万トン)をやや上回った。
本年の価格のピークは初漁期が低調なため、新物入荷量が少なかったため以前のように8月にみられた。その後例年同様入荷のピークを迎える9月に入って急落し、10月以降は昨年同様大幅な下げもなかったが、昨年同様水準としては低かった。
平均価格は生458円(前年449円)、冷319円(前年323円)、塩470円(前年531円)であったが、生鮮のみが入荷の減少を反映し上げたが、冷凍、塩干何れも入荷の多さを反映しやや下げた。また消費支出をみると、産地水揚げや消費地入荷が減少している割には前年を上回っており、末端での根強い需要の存在があることがわかる。
輸 出 入
本年の輸入は、10,429トンで前年(903トン)を大幅に上回った。
これは漁期が始まってから魚体が当初小さかったことにより、輸入に走ったもので特に10月以降に急増しており、昨年を除いた例年のパターンに回帰している。主要な輸入国は台湾からが90%以上で殆どを占めており中国からも急増して若干みられた。
輸出はH4年をピークに近年減少傾向が続いていたが、本年は1.8万トンと近年で最も高い水準であった前年(2.4万トン)を下回ったもののり好漁を反映し大幅に増加した。
価格も、輸入137円(前年230円)、輸出101円(前年106円)で何れも前年を下回った。
本年は周年を通じてコンスタントに輸出されており、時期的な集中はみられなかった。
本年も韓国が最も多く、トリニダッドドバコ、中国、フィジー、台湾、サモア、米国向けとなっているが、中国向けが多くなっている。