02�N�@�C�J��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�ʁF���ʁC1000�g���A���i�C�~�^kg
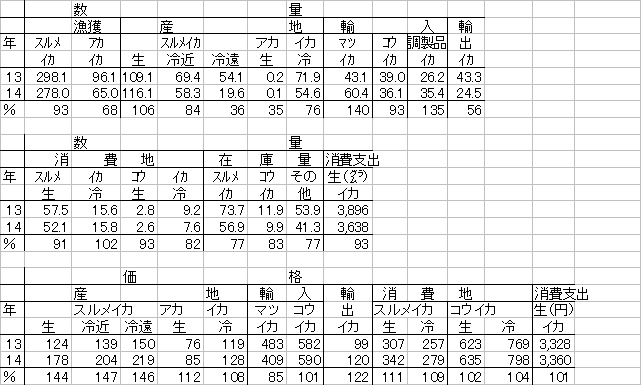
�X�@���@���@�C�@�J�@�́@���@��
�@
�����N��ɓ����ē��{�ߊC�̃X�����C�J�̋��l�́A����10�N�������Ƃ��Ȃ����I�ɐ��ڂ��Ă���20�`40���g����̍����������L�^���Ă���A�{�N�����̔��e�ɓ����Ă���B
�����m���̋��l�̖w�ǂ��߂�~���܂�Q�́A1950�`60�N��Ƀs�[�N���}�������A���̌�80�N��ɒᐅ���ƂȂ�A89�N�ȍ~�����ɓ]���A90�N��ɓ����Ē��`���ʂ̐����ň��肵�Ă����B�������A98�N����]�}���������A���̌�}���ɉX�����݂��Ă���B������2001�N���Q��2000�N���Q�Ɠ������x�Ɛ�������Ă���A2002�N���Q���͍��ʉ����ƌ����Ă���B
�@��ɓ��{�C�i�Δn�g���n�j�ŋ��l�̑ΏۂɂȂ�H���܂�Q�̎��������́A1970�N��̌㔼����86�N�܂Ō����X���ɂ��������A1987�N�ȍ~�A1998�N�Ɉꎞ�I�Ɍ����������A1999�N�ɉE�����������ێ����A2000�N�A2001�N�͋ߔN�ł͍ł������l��2002�N���������̂Ƃ݂��Ă���B���������Č��݂̎����͍������ő����X���ɂ���Ƃ����Ă���B
�Y�@�n�@���@�g�@�ʁ@�Ɓ@���@�i
14�N�̓��{�ߊC�̃X�����C�J���g�ʁi49�`�j�́A11.6���g���i�O�N10.9���g���j�A��5.8���g���i�O6.9���g���j�Ɛ��N�͂����A�Ⓚ�͌��������B�������A�������������ł̒��ł̋��l�ł���A�{�N(���A��)�̓g�[�^���Ŏ���������Ƃ����Ă������ď��Ȃ������ł͂Ȃ������B�����āA�����m�ł̋��Ǝ�ޕʂɂ݂Ă��A�g���[���A�܂��Ԃ��O�N�ȏ�̍D���l�A�ނ肪�������݂����̂̂���Ȃ�̋��l�ł͂������B�Ⓚ�́A�{�N����N���l�k���D�c���唼���X�����C�J�A�X�A�k�C���A���D�c���A�J�C�J�i�����T�L�C�J�j�Ɠ������番�U���Ƃł��������A�{�N��N�Ɉ������ԃC�J���s�U�ŁA�O�N���݂̋��l�ɏI����Ă���B
���}�C�J�̊C��ʋ��l�ʂ́A���{�C16,822�g���i�O�N20,510�g���j�A�����m87,353�g��(�O�N77,442�g��)�A�I�z�[�c�N2,061�g���i�O�N1,142�g���j�ł������B�{�N�̓����́A��N�Ƃ͋t�ɂȂ���{�C�̌����A�����m�A�I�z�[�c�N�C��Ƃ������ł������B�܂��ߔN�������Ă����B�k���ł̋��l��9,677�g���őO�N(9,778�g��)���݂ł������B�@
�{�N�����^�D���D�́A�����X�����C�J�ƃA�J�C�J���ƂƂɕ����ꂽ���A���̌���������Ă̑��ƂŁA�T�˓��{�C���Ƃ���̂œ��{�C�ł̂���߂������͏����ȋ����������B
�@�܂��{�N���ƊE�ł́A�]������X�����C�J��ɏW���̔r���A�O�ɋ���̑I��I�ړ��A�t�����l�̍��������i���̏���A�T�C�Y�I�̎w���͖{�N���������B
�Y�n���i�́A���N178�~�őO�N�i124�~�j�A�Ⓚ��204�~�ƑO�N�i139�~�j��������������B
�{�N�̓����́A�@���N����␅�g���������݂�ꂽ���A�����m���ł͍�N�ɑ����ė��P���傫�������������A�g���[���A�܂��Ԃ��n�߁A�ނ�Ƃ��D���̕��ނł����������A�A�{�N�̗Ⓚ�̃T�C�Y�g���́A21�`25���T�C�Y��31%�őO�N�i19%�j������A26�`30�T�C�Y��26%�őO�N�i28%�j��⏭�Ȃ����x�A�T�C�Y�g����20���ȉ���18%�őO�N�i11���j��葽���A�����đ�^�����Ă������ƁA�B�`�q�C�e�n�q�A�y���[���擙�A�C�O�ł̃C�J�ނ���N�Ɉ������ᒲ�ȋ��ŁA���ɂ`�q�C�e�n�q�ł͔����������ƁA���ł���B
�݁@�Ɂ@��
14�N�͑O�N����8.5���g���̌y���ɂ���n�܂�A�㔼���͊C�O�C�J�̒���ōɂ͏����ɏ����ŗ�N�ʂ�6���ɍŒ�ł��������A���̐��ʂ�3,8���g���ŋߔN�ł͍Œ�̐����ł������B���̌�A�V���̐��g�����n�܂��������珙�X�ɑ����������A�{�i�����n�߂��H���ɂ͗�N�̂悤�ɍɂ��c����A�z�N�ɂ�7.3���g���ƊC�O�C�J�̋��������������������A�ߔN�ł�1998�N(6.4���g��)�Ɏ������Ȃ��ł������B���������ĕ��ύɗʂ��A5.5���g���ŁA�O�N�i7.4���g���j��傫����������B
���@��@�n�@���@�ׁ@�ʁ@�Ɓ@���@�i
�X�����C�J�̏���n���חʂ́A��5.2���g���i�O�N5.8���g���j�A�Ⓚ1.6���g���i�O�N1.6���g���j�ł������B�{�N�͎Y�n�ł̋�����r�I�D�����������O�N�ɂ͋y�Ȃ����̂̐��N�������������A�Ⓚ�͍��l�ɂ��S��炸�C�J�ޑS�̂̋����ʂ̌�������A�O�N���݂��ێ������B ���i�́A��342�~(�O�N307�~)�A��279�~(�O�N257�~)�Ő��E��Ƃ��v���U��ɋ��܂B
����x�o�ł݂�ƒP�����̉e�����čw�����ʂ̌������݂�ꂽ���̂̋��z�x�[�X�͔����ƂȂ����B
�m�y�C�J
14�N�̂m�y�C�J�ދ��́A���ɖ{�N�x�̏o���͂Ȃ��Ȃ����B���݂ɑO�N�͂P�ǂ̑��Ƃ�262�g���ŁA�P�Ǔ���̋��l�ʂ�262�g���ł������B
�r�v�`�C�J
14�N�̂r�v�`�}�c�C�J�ދ��́A�`�q29�ǁ|11,365�g���i�O�N33�ǁ|44,822�g���j�A�e�n�q19�ǁ|5,611�g���i�O�N14�ǁ|18,176�g���j�ASA���C29�ǁ\11,365�g���i�O�N33�ǁ\7,675�g���j�ł��������ASA���C�������Ζ{�N�͍�N�ȏ�ɒᒲ�ŁA�t�H�[�N�����h�A�A���[���`���Ƃ��啝�Ɍ������݂��B
�@�Y�n���g�ʁi�S���A�j�́A19,472�g���őO�N�i53,139�g���j��傫����������B
���i��220�~�őO�N�i150�~�j�����Ȃ�������B�{�N�́A�啝�Ȑ��g���̌����f��2�N�����̏㏸���݂����A��N�ȏ�̏グ���ɂȂ����B
�A�J�C�J
�{�N���A�s������甲���o�����Ƃ��ł����A���������̉ď�Ɉꎞ�I�ɋ�����܂Ƃ܂������A���̎����ł���N�ɋy���A���̌�̗�N���l��������H����~��ɂ����đS���ᒲ�ɏI������B�ߔN�ł��ł����Ȃ����g���ł�������N���X�ɑ傫����������B�܂��A�{�N�͏��^�D����N�ȏ�ɂ݂�ׂ������Ȃ��A�قڊF���ł������B�Ȃ��A��^�D�i�������Ɓj��4��1,629�g���ŁA�O�N�i24��2,981�g���j������������A1�Ǔ�����̋��l�ł͑O�N��傫������A�ߔN�ł͍ł����������B
�S���A�W�v�ɂ��ƁA��3�g���i�O�N111�g���j�A��0.9���g���i�O�N1.5���g���j�ł������B
�Y�n���i�́A��45�~�i�O�N55�~�j�A��294�~(�O�N301�~)�ł������B
���g���̌��������������Ă��邱�Ƃ������Ė{�`�����͖{�N�������������������B
�@�C�O�Ԃ����́A�y���[�̂�(200�C�����O)�̑��Ƃł��������A�v�X�A17��-33,217�g���A27��-29,733�g���ŁA��N���сi33��-84,041�g���A12��-2,082�g���j�Ō��C���������݂̂�,200�C�����ł͒ᒲ�ł������B
�@�{�N�̃T�C�Y�A�\�[�g��5���ȉ���52%�i��N��6-10���T�C�Y56%�j�ƒ�����T�C�Y�ɕ�A
����^�������B
�A���C�J
�@14�N�̗A���C�J�́A���������̏��Ȃ��f���A6���g���ƑO�N�i4.3���g���j�����Ȃ�������B
���i�́A�����̑����f��������������409�~�ƑO�N�i483�~�j����������B
�Ⓚ�C�J�̎�v�A�����́A�C���h1,925�g���i2,965�g���j�A�č�8,947�g��(�O�N5,567�g��)�A�x�g�i��4,557�g���i�O�N3,722�g���j�A����16,655�g���i�O�N16,448�g���j�A�����b�R1,592�g���i�O�N1,637�g���j�A�^�C9,464�g���i�O�N8,211�g���j�ANZ2,785�g��(�O�N768�g��)�AAR9,720�g��(�O�N58�g��)�Ŗ{�N�͕č��A�x�g�i���̑����A�C���h�̌����X���A�܂����p�D�̕��ŃA���[���`������̑����������ł������B
14�N�̗A�o�́A2.4�g���őO�N�i4.3���g���j��啝�ɉ�������B����͍��������ʂ��C�O�C�J�̕s�U�ɂ��A�����������̂ł���B
�����S�C�J
14�N�̃R�E�C�J�̗A���́A3.6���g���őO�N�i3.9���g���j����������≺����Ă���A�{�N�����̌X���ɕω��͂Ȃ��B
���i�́A590�~�őO�N�i582�~�j���݂ł������B
����n���חʂ́A0.8���g���ŗA���̌����▖�[���v�̔�������֕i������A�������O�N�i0.9���g���j����������B
���i�́A798�~�ň����̌����f���đO�N�i769�~�j���������Ă��邪�A���̂Ƃ���W�����X�����ڗ��悤�ɂȂ��Ă��Ă���B