2001�N�T�o��![]()
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �P�ʁF���ʁC1000�g���A���i�C�~�^kg

���l�Ǝ���
�@13�N�̃T�o�ށi�}�T�o�ƃS�}�T�o�j�̋��l�ʂ́A40���g���O��Ƃ݂��O�N(34.6���g��)�������������̂Ƃ݂��邪�A�ߔN(�����N��̕���50���g��)���ˑR����鐅���ɂƂǂ܂��Ă���B
�@����́A�R�A�������e�n�ł�⋙�l�������������Ƃɂ����̂ł���B
�@���{�̃T�o���l�ʂ̑����́A���Ă͖k�������m�C��⓹���C��ł̋��l�����ɑ傫�����E����Ă������A�ߔN�S�̓I�Ɏ��������X���������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����A���V�i�C��R�A�ł̋��l�������傫�ȉe����^����悤�ɂȂ��Ă��Ă���B
�@�}�T�o�����m�n�Q�̎����͈ˑR�ᐅ���ł���Ƃ����Ă���B1980�N�㖖�ɍĐ��Y�������̒ቺ�ɔ��������ʂ̌����Ƌ������l���ɂ�茸�����A�ߔN�̎����ʂ͒ᐅ���ł���B����1996�N���Q����z�N���Q�Ƃ����Ă��邪�A���̌�͂�������z�N���Q�͏o�����Ă��炸�A�ᐅ���������Ă���B�S�}�T�o�̎�����1999�N�A2000�N���Q�Ƃ��ɑO2�N�ɔ�ׁA�����Ƃ����Ă���B
�܂��A�Δn�g���n�Q�̎����́A90�N��ɓ����đ����������A97�N�ȍ~�����ʂ̌�����97�N�ȍ~�͎Y���e�����������Ă���A2000�N�ɑ啝�ȋ��l�̌����Ɍq�������̋L���ɐV�����Ƃ���ł���B
�Y�n���g�ʂƉ��i
�@13�N�̎Y�n���g�ʁi42�`�j�́A30.6���g���őO�N�i21.5���g���j�����Ȃ�������B
�@���i�́A81�~�őO�N�i105�~�j�����Ȃ艺������B����́A�������̑����A�ˑR�^�������������A�S�}�T�o�̊����̑����A���v�������������C���i�P���A�ʂƂ��j�ł��������ƁA�������ʂɂ����̂ł���B
�@
�C��ʋ��l��
�{�N�̊C��ʋ��l�̓����́A���\�̒ʂ�O���A��ցA���C�E�쐼�A�F��A���V�i�C�ŋ��l�̑����A�R�A�݂̂����Ȃ苙�l�����炵�����Ƃł���B
���ɍ�N�܂��Ԏn�܂��Ĉȗ��̕s�U�ł��������C�ł̋����~��̐������ɂ������������ƂƁA��֊C��ŏt��Ɠ~��̓쉺�Q�̋��l���D���őO�N��啝�ɏ��������ƂȂǂ�������ł������B
�C��ʋ��l��
|
|
|
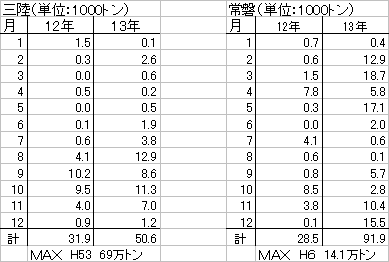
�O�@��
�@�{�N�̖k����̋��́A�����Ă悢�ł͂Ȃ��������A��N���͂��ǂ������B�H�T�o���͂V�����{�ɖk����̃W���~�T�o�����l���ꂽ���̂̂W����{�ɒ��T�o�i31�`33�p�A470g�j�����l���ꂽ�̂���ɍ�N�������鋙�ł������B�{�N���W����{����X�����C�J�̍��l��10���̏�{�܂ő������B
�@���̂͋����O���̂W���ɂ͒����^��(29~33�p)�����l���ꂽ���A�X���ȍ~�͂P���i2000�N���Q�j��30�p���[�h����̂ɕς�����B�����ė�N�����㔼�ɋ��l����铖���͖w�ǂ݂��Ȃ������B
�@�܂��A�{�N���X�����C�J���I�����10���̒��{�ȍ~�͖{�N���u���i�C�i�_�A���J�V�j�̋��l��8���ȍ~�f���I�Ȃ����12�����{�܂ő������B
��@��
��N�Ƃ͈Ⴂ�쉺�Q�̎c��̉z�~�T�o����r�I�D���ɐ��ڂ��A�z�~���T�o��37.8��g���őO�N(10.6��g��)��啝�ɏ������B
�@�������A�t�i�T�`�V�����j�̖k��Q�͉z�~�Q���l�ᒲ�ŁA19.7��g���ŋɂ߂Ĉ��������O�N(4.7��g��)��啝�ɏ������B
�쉺�Q�̋��l��28.7��g���őO�N�i12.4��g���j��啝�ɏ���A���N�͑S������ʂ��Ĕ�r�I�D���Ȑ��ڂł������B�Ȃ��A�{�N��12���ɂ̓C�i�_�̋���`�����݂�ꂽ�B
���̂��A�z�~���ɂ�1���i2000�N���Q�j�A�k����ɂ�1���i2000�N���Q�j��̂�2���i99�N���Q�j������A�쉺���ɂ̓S�}�T�o����̂ɕς��1���i31�`33�p�j��̂ɓ����i26�`28�p�j������ł������B
�@���ɖ{�N�́A���Ă���~��܂ł���̂ɃS�}�T�o�̍��l���ڗ����đ��������B
���@�C�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�ɓ��������ӂ��務��Ƃ��āA��ɎY���Q��ΏۂƂ���T�o�^���������Ƃ́A54�N��17.7���g�����s�[�N�Ɍ������Ă���A�ߔN��1���g���ȉ��̒ᒲ�ȋ��l�������A���Ɛǐ��������ɔ�ב啝�Ɍ������Ă���B
12�N�̋��l�ʂ́A�}�T�o���قڊF���i0.2�g���j�ň��������O�N35�g���������A�S�}�T�o7,790�g���i�O�N6,007�g���j�Ń}�T�o���j��Œ�̐��g������������9�N������鋙�n�܂��Ĉȗ��̍Œ�ł������ 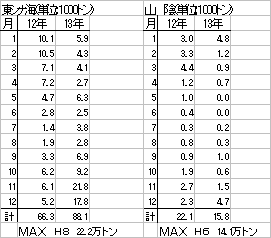
|
|
���@�V�@�i�@�C
�@13�N�̋����́A�N������̓~���͑O�N���̋����f���ᒲ�ŁA�O�N�����Ȃ艺��鐅�g���ɏI������B�܂��ď�̋����O�N�������������x�Œᒲ�ł������B���������̌�̏H����9���ȍ~�܂Ƃ܂�n�߁A�~��̐��������}����11���ȍ~�͋��l�̐L�т��݂��A�ᒲ�������O�N�̂R�{�ȏ�̐��g���ƂȂ����B���������ĔN�Ԃ̐��g�ʂ��A�O�N�����Ȃ�������B�����������g�ʂ̐����Ƃ��Ă͕K�����������͂Ȃ��A�ߔN�ł�12�N�Ɏ����Ⴓ�ł������B
���̂́A�{�N���T�˃M���A���[�\�N�T�o�i0�1���j�����l�̎�̂Ŗ�70�����ł��������A
�O�N (55���O��)��肩�Ȃ葽���Ȃ��Ă���A���̐��N���ɏ��̊����������C���ł��������̂́A�ēx���^���̊����������X������B�܂��A�{�N�͏��^���̑����������ŁA���̂�400g�A�b�v�^�̑�E���T�o�͍�N��菭�Ȃ����g���ł������W����T�ˊe�T�C�Y�Ƃ��O�N�ȏ�ɉ��i���㏸���Ă���B�@
�R�@�A
���̊C��ł́A��N������鑍���Ēᒲ�ȋ��l�ŏI������B
�@�{�N�̋����̌o�߂́A�N������̋��͑O�N���݂ɐ��ڂ������A���̌�̔~�J�O�̏t�����ᒲ�ō�N����≺������B�ď�ȍ~�������̋����A�N���ɂ���オ�����݂̂ň�������N���݂ɒᒲ�ł������B
���̂́A2000�N���Q��̂ɁA�O����1999�N���Q�A�㔼�ɂ�2001�N���Q���������Ă����B
�A�@�@��
�T�o�̗A���́A���{�ߊC�̃T�o�����̒���⋛�̂̏��^���ɔ����}�����A���ł�10�N�ȏ�̗��j���o�߂��Ă���B�����Ăr61�N�i1.1���g���j�ȍ~�������Ă���B���̗A���吼�m�T�o�́A���b����������ɉ��T�o�A�t�B���[���i���n�߁A�Y�T�o�E�ϕ��E�ĕ����ɂ����p����Ă���B�܂��ŋߗʔ̓X�ł͗Ⓚ�t�B���[�̐�g�ł̓W�J������A������ɕω��������n�߂Ă���B�܂����H���[�J�[�ł͉��T�o�����w�t�B���[�ɐ�ւ����i��ł���B
�{�N�̗A���ʂ́A17.4���g���ŁA�O�N�i15.9���g���j���������B����͎�ɏ㔼���ɂ�����V�[�Y�����ȊO�̗A�������̂��߂ŁA�H���̗A���ʂ͂قڑO�N���݂ł������B
�@��v�ȗA�����͑O�N���l�{�N���m���E�F�[��91%�Ƃقڈ�ɏW�������Ă���B�܂��A����ȊO�ł̓A�C�������h�̑������{�N�͖ڗ���3400�g�����A�f���}�[�N�����3200�g�����A�C�M���X�����2600�g�����ł������B�{�N�͑吼�m���ł̓m���E�F�[��200�C���O�ł̑��Ƃ������������Ƃ����������B
�@�{�N�̃m���E�F�[����̗A��������600�T�C�Y�ȉ���70%�i�O�N:81%�j��̂�600�t�o��30%�i�O�N:19%�j�ŁA600�t�o�������A4-6�T�C�Y�̌����ƂȂ��Ă���B
���i�́A146�~�őO�N(112�~)�����������A�m���E�F�[���n�s���̏㏸�f�������̂ł���B�܂��A�{�N�͓��{�ȊO�̃��V�A���n�ߓ��������ł̔��t�����������Ă��邪�A�t�ɒ����݂̂��������Ă���B
�ߔN�A�����A�^�C���C�O���H���ˑR�����ɂ݂��A���i�A���������Ȃ��Ă����ɁA�������H���[�J�[�̒����i�o�������Ȃ�A�A�����ƍ������H���Ƃ̔̔���������w�������Ȃ��Ă���B�����ɍ������H�Ƃ̋����ڗ��悤�ɂȂ��Ă��Ă���B
�A�@�o
�@�{�N�̗A�o�ʂ́A4.1��g���őO�N(2.5��g��)���������B����͍������̎�̉f�������̂ł���B�܂��A�ʋl�A�o��3.8��g���ƂقڑO�N(3.9��g��)���݂ł��������ߔN�̒ᐅ���̘g���Ő��ڂ����B
�݁@�Ɂ@��
�@ �ɗʂ́A8.4���g���ƑO�N(9.5���g��)���������O�N����≺������B
�@����́A�A���ʂƍ������Y�ʂ������������̂́A���N������Ⓚ�����Ƃ��Ă̔�r�I�������i���Ƃf�������̂ł����B
����n���חʂƉ��i
�@ 13�N�̏���n���חʁi10��s�s�j�́A�Y�n�ł̋��l�����������Ƃ������r�I�R���X�^���g�ȓ��ׂ������A���N5.5���g���ƑO�N�i5.1���g���j�����������B�܂��A�Ⓚ��1.9���g���i�O�N1.6���g���j�A����4.3��g���i�O�N4.2��g���j�A����1.4���g���i�O�N1.5���g���j�Ɖ����������T���͉����X���ł������B
���i�́A���N324�~�i�O�N388�~�j�A�Ⓚ284�~�i�O�N287�~�j�A����503�~�i�O�N519�~�j�A����453�~�i�O�N445�~�j�ł������B
���i�́A�A���������i���㏸���������i���t�B���[��g��ۂŗ��p�j�݂̂���グ���ق��́A������A���N�A�Ⓚ�A�����Ƃ������Ⴕ���͂�≺�����������B
�@�܂����ɖ��[�̃X�[�p�[�E�ʔ̓X�ł́A�����f���A�S�}�T�o�̃t�B���[���g�̔̔����ߔN�ɂȂ��ڗ����đ����Ȃ��Ă��Ă���B
