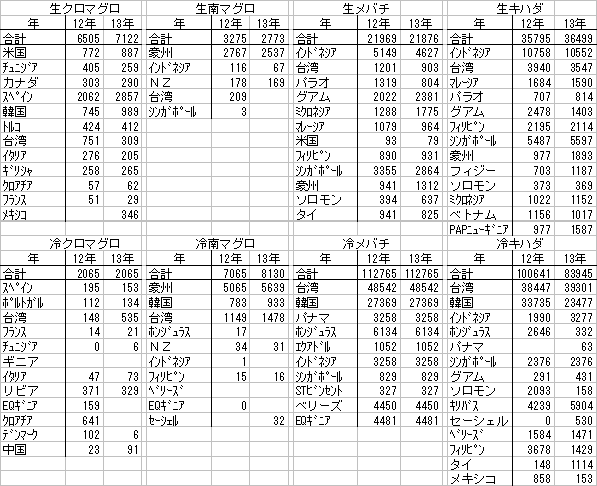2001年マグロ類
単位:数量,1000トン、価格,円/kg
漁獲量
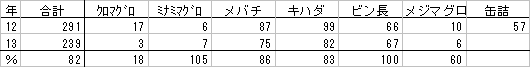
産地水揚量(42港)
流通統計
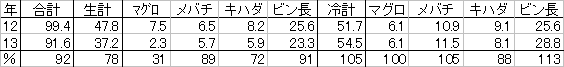
輸 入 量
通関統計
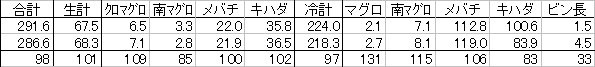
輸 出 量
通関統計
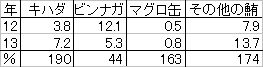
消費地入荷量(10大都市)
流通統計
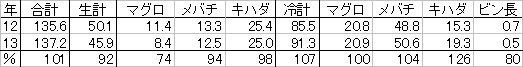
全国平均世帯の消費支出 (総務庁家計調査)
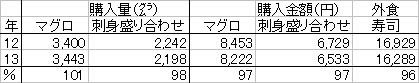
月平均在庫量
流通統計
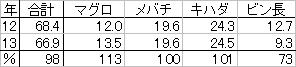
産地水揚量(42港)
13年のマグロ類の産地水揚量は、9.2万トンで前年(12.8万トン)をかなり下回った。
生鮮は、で前年3.7万トン(4.8万トン)を下回った。
これはこの2年間好調に推移していた近海まき網クロマグロが不漁で水揚げを大幅に減らしたのとまき網や延縄のキハダが極めて低調であったことを反映したものである。
また、近海のメジマグロは、近年好調であった日本海、九州西部で低調に推移し、昨年と反対では夏場の三陸沖で昨年をやや上回って推移した。
冷凍はで5.5万トン前年(5.2万トン)をやや上回ったが、この増加は黒潮前線漁場から東沖漁場での近海ビンナガ漁が好調であったことを反映したものである。また今年の西経域を主体とする大型延縄船の漁は、メバチ、キハダが昨年同様やや好調であった。ただ、アソートもキハダが多くなっているといわれ、刺身用良品が少なくなっている模様。また大西洋、インド洋とも低調で、唯一12月にソマリア沖でキハダの好漁がみられたことが特徴であった。また本年のケープ沖、豪州周辺の南マグロ漁は前年よりやや良い程度で不安定、大西洋北部のクロマグロもかなり不振であった。
日本海マグロ水揚実績(境港)
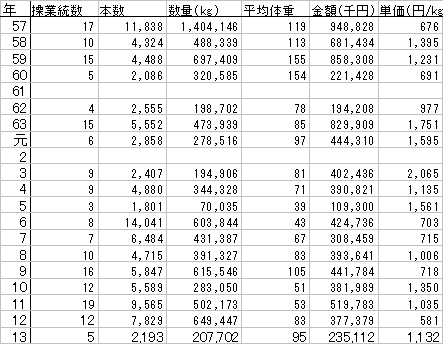
輸入量
13年の輸入は、28.7万トンでほぼ前年(29.2万トン)並みの大量搬入であった。
本年は生鮮のクロマグロの増加、ミナミマグロの減少、冷凍のクロマグロ、南マグロの増加となったほかは大きな変化なく、冷凍キハダが減少した程度であった。は好漁とアソ-トの変化もあり大量の搬入増加であった。また、脂身物や上赤身物の減少に伴い、年々蓄養物が増加しているが、特に生鮮物の中での蓄養物のシェアーも高くマグロもやや増加したがなっており、トロビンナガ等とともに、その値頃感もあって伸びが目立っている。したがって、蓄養マグロは98年7000千トン、99年1.3万トン、2000年1.6万トン、2000年は2万トン前後とみられ、着実に増加している。
また赤身系のメバチの蓄養物も本年初めて築地に搬入されるなど、赤身の蓄養拡大の動きも注目されるところである。
在庫量
本年の月平均在庫(ビンナガも含む)は、6.7トンでほぼ前年(6.8万トン)並みであった。
本年は、前年来のキハダとメバチの在庫が依然多かったのを始め、脂身系の南マグロ・本マグロも前年以上に多かった。しかし、ビンナガは前年後半の漁不振の影響が上半期の在庫の少なさにつながり、減少傾向が顕著であった。
消費地入荷量
13年の消費地入荷量は、13.7万トンでほぼ前年(13.6万トン)並みであった。
本年の特徴は、生鮮では、国内まき網漁が不振であったマグロ(クロマグロ、ミナミマグロマグロ)がかなり減少したほかは、ほぼ前年並みであった。
冷凍は、在庫が多かったキハダの入荷が目立って多かった以外は、ほぼ前年並みであった。
価格 (単位:円/kg) 流通統計
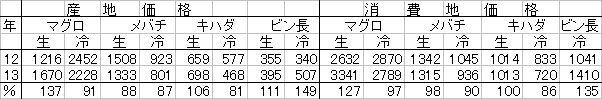
13年の産地価格は、生鮮では1990年以降もっとも低調であったキハダと同じく過去2年間の好漁から一転不漁となったマグロの上伸が目立ったほかは、メバチが弱含んだ。
冷凍は、秋口に高騰したビン長のみがやや上伸したほかは、本年は、在庫の多かった赤身類、脂身とも浜値は下落が顕著であった。
またビン長はすっかり消費需要も定着し、「色へのこだわりから実質」へと消費者の感覚も変化しているようで近年は強含み推移が目立ってきている。
13年の消費地価格は、生鮮マグロと冷凍ビン長が産地同様大幅な上昇となったが、その他については概ね前年並み若しくは前年を下回る動きであった。
また、本年も昨年同様、赤身商材のメバチ、キハダは安値定着化の中で周年特売商材としての利用されており、特に末端では土曜、日曜の消費は多かったものと見られ、マグロの購入量は前年並みの消化となっている。しかし金額は減少しており、単価的には市場価格と連動して下げている。
日本近海(北部太平洋海域)まぐろ魚体組成
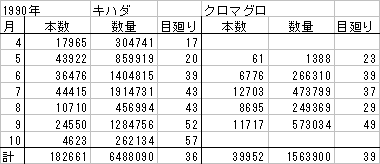


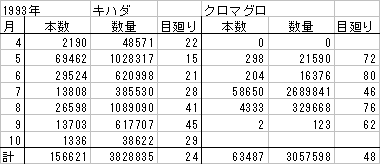

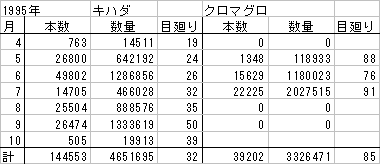
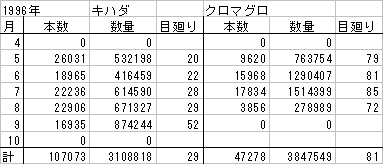
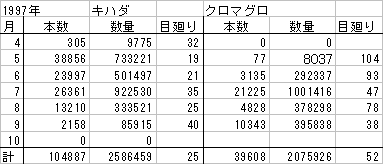
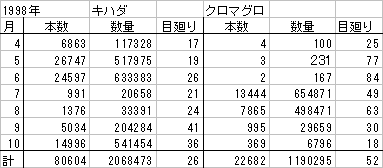



資料:輸入マグロ類の実績