2001年カツオ
単位:数量,1000トン、価格,円/kg
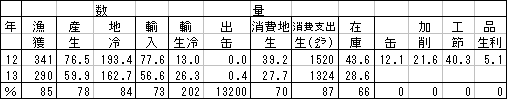
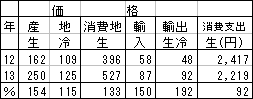
漁業・資源・漁獲
日本のカツオ漁業は、千葉以南の沿岸や伊豆諸島周辺で行われている曳縄を別にすると大別し一本釣りとまき網に分けることができる。また、カツオの漁獲量の大半がこの2つの漁種により占められている。
昭和39(1964)年南方竿釣り漁業が周年操業化、同45(1970)年の開発センターの調査を境にして同49(1974)年に海巻き操業の本格化がみられ、漁場は南及び東方にも拡大し、10゜S以北、155゜W以西の中央〜西部太平洋で広範囲に形成されている。更にインド洋(現在は撤退している船も多い)、タスマニア、ニュージー海域での操業もみられるようになり、その比較的豊富な資源量と品質的安定もあり、特に海巻物は節業界にとっては輸入物としての搬入もあるが、貴重な加工原料となっている。
1970年代以降増加を続けていた中西部太平洋の漁獲量は、1988年に50万トンを越え1990年代に入り、100万トン前後の漁獲で横ばい傾向であったが、1998年以降更に高水準とされ、CPUEに明瞭な減少傾向がみられないことや、標識放流データを用いたモデル計算でも開発の余地があること、などが報告されており安定した資源状態を維持しているといわれる。しかし世界的な魚価低迷の中、経済的要因で漁獲努力の調整がいわれている。インド洋の資源も、1983年の6万トンから1994年の31万トンへと急激に増加し、その後の漁獲量も25万トン前後とやや減少したが、1998年に再度31万トンと再度増加しつつある近年、漁獲の約半分を巻網(フランス、スペイン、日本)残りを(モルジブの竿釣りとスリランカの流し網)でとっているが、概ね健全であるとの評価がなされている。
また、近年南方漁場では、日本船以外の外国船も多く操業がみられ、その漁場は主にニューギニア海域となっている。海巻の勢力は、西部太平洋では主に日本、台湾、韓国、米国、フィリピン、ミクロネシア、ソロモン、バヌアツ、豪州、ロシア、その他、東部太平洋ではメキシコ、エクアドル、ベネズエラ、バヌアツ、米国、コロンビア、その他ベリーズ、キプロス、ホンジュラス、中国、スペインが、東部大西洋ではスペイン、フランスのまき網、ガーナ、スペイン、ポルトガルの竿釣り、西部大西洋は主にブラジルの竿釣りが操業を行っているが、この海域では本格的解析がないが、全体としては過剰漁獲には至っていないといわれている。また世界的に過剰供給による魚価低迷もあり、本年3月に世界カツオ・マグロまき網機構(WTPO)が設立されている。
また、国内供給問題では、従来の生食用のB1カツオに加えて、9年前から海巻B1(PS)製品の生産もみられ、量的にはB1に比べるとまだ少ないものの、末端の特売用商材として既に定着化している。特に魚価が安くなった場合はPS製品製造が多くなり、釣りとの競合問題が取りざたされるのが実態である。
本年のカツオの漁獲量は、30〜45万トンについで多い部類の30万トン弱と推定される。
産 地 水 揚 量 と 価 格
13年の産地水揚量は、22.3万トンで前年27万トンを下回った。
内訳は、生6万トン、冷16.3万トン(前年:生7.7万トン、冷19.3万トン)であった。
本年の生鮮(日本近海)の漁況は、初漁期(1〜4月:犬吠埼以南の本邦南岸域漁場)の釣り漁場は悪かった昨年をやや上回ったものの依然水準としては低かった。
その後、黒潮前線を越えてからの三陸・常磐沖での漁は、6、7月に昨年並みの漁獲をみたが、秋口に昨年のようなまとまった水揚げがなく急激に低調になった。その結果、漁獲は釣、まき網とも昨年をやや下回った。
海域別漁獲量は、三陸75%(前年:70%)、常磐13%(前年:16%)、南西・東海3%(前年:6%)、九州西部7%(前年:5%)九州南部2%(前年:3%)であった。

本年も漁場形成の主体は前年以上に三陸・常磐海域であり、その他の海域は大きな変化はみられなかったが、九州西部での漁獲の増加が顕著であったみられた。
冷凍は、竿釣り、海巻きとも減少が顕著であった。また、本年の海巻きは、引続きメバチ(ダルマ)が増加傾向(前年の1.5倍)にあり、キハダも本年は増加した。釣りはビン長に対する回転すし等を始めとした外食産業等での需要増加もあって人気は高いが、本年も東沖トンボ漁への漁獲努力も恒常的にみられ、漁獲の増加がみられたが、品質的に良品が少なかったといわれている。
価格は、生250円(前年162円)、冷125円(前年109円)で推移したが、生、冷とも昨年のセーフガードの声をよそに漁獲の減少を反映した結果となった。
消 費 地 入 荷 量 と 価 格
13年の消費地入荷量(10大都市)は、2.8万トンで前年(生3.9万トン)をかなり下回った。本年は昨年とは逆に産地での並み漁を反映した結果である。
カツオはサンマと並んで、大衆魚の中では現在でも比較的旬がみられる代表的な魚でもある。しかし、近年B1製品の普及で市場外流通主体の「タタキ」や東沖「トロカツオ」、「トロビン」も定着している。
本年は漁獲が少なかったことと高値でもあり、秋口の入荷の減少が目立ち昨年のような5月以降の入荷増加が極端ではなかった。しかし1998(平成10)年以来、6月の入荷量が5月より多かったのが特徴。
しかし、近年の傾向である三陸の「下りカツオ・戻りカツオ」の消費の広がりもあって秋口(9、10月)に消費地市場への入荷もそれなりにみられている。
価格は、527円で産地水揚げの減少を反映し、前年の396円をかなり上回った。
輸 出 入
カツオの輸出は、原魚と缶詰に分かれるが、缶詰輸出は既に国際競争力を失って久しくなっており、国内漁の如何を問わず依然非常に低水準である。したがって、原魚の大半が海外缶詰生産用の輸出となっている。
本年は、原魚2.6万トン(前年1.3万トン)、缶詰396トン(前年2.5千トン)であったが、原魚輸出は国内漁が並漁であったものの、タイを中心として需要があり倍増した。
輸入は平成年度に入ってから円高傾向もあって年々増加傾向がみられていた。これは節用需要の高まり(竿釣船のB1化に伴い国内の需要を満たしきれなくなった)で量、価格、品質とも安定している輸入物への依存度が高まっているためである。しかし本年は国内漁及び特に海巻物の不振がみられたものの、円安基調もあって輸入はかなり減少した。同時に昨年の輸入量の多さの中で製品在庫の多さもあると同時に、需要の減退もおきている可能性も少なくない。したがって、本年の輸入量は5.7万トン(前年7.8万トン)であった。
価格は、87円で前年(58円)を大きく上回った。世界的な市況の回復によるものである。