2001�N�C�J��![]()
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�ʁF���ʁC1000�g���A���i�C�~�^kg
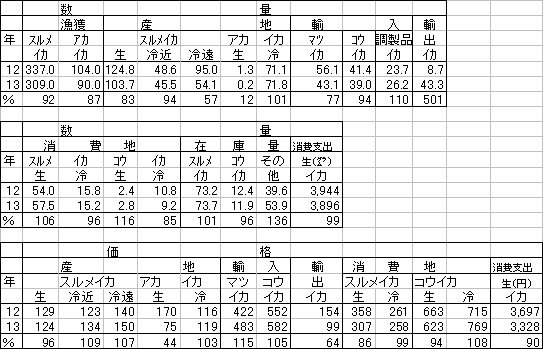
�X�@���@���@�C�@�J�@�́@���@��
�@
�����N��ɓ����ē��{�ߊC�̃X�����C�J�̋��l�́A����10�N�������Ƃ��Ȃ����I�ɐ��ڂ��Ă���20�`40���g����̍����������L�^���Ă���B
�����m���̋��l�̖w�ǂ��߂�~���܂�Q�́A1950�`60�N��Ƀs�[�N���}�������A���̌�80�N��ɒᐅ���ƂȂ�A89�N�ȍ~�����ɓ]���A90�N��ɓ����Ē��`���ʂ̐����ň��肵�Ă����B�������A98�N����]�}���������A���̌�ēx�X�����݂��Ă���B������2001�N���Q��1996�N���Q�Ɠ������x�Ɛ�������Ă���A���ݐ����͍s�����ƌ����Ă���B
�@��ɓ��{�C�i�Δn�g���n�j�ŋ��l�̑ΏۂɂȂ�H���܂�Q�̎��������́A1970�N��̌㔼����86�N�܂Ō����X���ɂ��������A����ȍ~1998�N�Ɉꎞ�I�Ɍ����������A�����������ێ����A2000�N�͋ߔN�ł͍ł������l�ŁA2001�N��2000�N���l�������̂Ƃ݂��Ă���B���������Č��݂̎����͍������ʼn����Ɣ��f����Ă���B
�Y�@�n�@���@�g�@�ʁ@�Ɓ@���@�i
13�N�̃X�����C�J�̐��g�ʁi42�`�j�́A10.4���g���i�O�N12.5���g���j�A��4.6���g���i�O�N4.9���g���j�Ɛ��N�E�Ⓚ�Ƃ����������B����́A�O�N�̋��l���̂��ߔN�ł�����߂č��������ł��������߂ŁA�{�N�͌��������Ƃ����Ă������ď��Ȃ������ł͂Ȃ��A�����m�ł̒ނ�A�g���[���A�܂��ԁA��u�Ƃ�����Ȃ�̋��l���������B�Ⓚ�́A�{�N����N���l�k���D�c���X�����C�J�A�X�A�k�C���A���D�c���A�J�C�J�i�����T�L�C�J�j�Ɠ������番�U���Ƃł��������A�{�N���{�`�����ԃC�J����������s�U�ŁA���{�C�⑾���m�}�C�J���Ƃɐ�ς��Ȃ���̑��Ƃ��������B
���}�C�J�̊C��ʋ��l�ʂ́A���{�C20,510�g���i�O�N16,884�g���j�A�����m77,442�g�� (�O�N97,030�g��)�A�I�z�[�c�N1,142�g���i�O�N6,124�g���j�ł������B�{�N�̓����́A���{�C�̑����A�����m�A�I�z�[�c�N�C��Ƃ������ł������B�܂��ߔN�͋�B�k���ł̋��l��9,778�g���Ƒ����������ɂȂ��Ă��Ă���B�@
�{�N�����^�D���D�́A�����X�����C�J�ƃA�J�C�J���ƂƂɕ����ꂽ���A���{�C�łقڎ��N�����ȋ����������B
�@�܂��{�N���ƊE�ł́A�]������X�����C�J��ɏW���̔r���A�O�ɋ���̑I��I�ړ��A�t�����l�̍��������i���̏���A�T�C�Y�I�̎w���͖{�N���������B
�Y�n���i�́A���N124�~�őO�N�i129�~�j�������A�Ⓚ��134�~�ƑO�N�i123�~�j�����������B
�{�N�̓����́A�@���N����␅�g���������݂�ꂽ���A�����m���ł͗��P�̌����������Ƌɒ[�łȂ��A�ނ�A�g���[���A��u�A�܂��ԂƂ��D���̕��ނł����������A�A�Ⓚ���A��⏭�Ȃ����x�łقڍ�N���݂̋��ŁA�T�C�Y�g����18�`20���A21�`25���T�C�Y��30%�ƑO�N�i33%�j�ƑO�X�N�i50���j��菭�Ȃ��A26�`30�T�C�Y��32%�őO�N�i38%�j��菭�Ȃ��������ƁA�B�`�q�C�e�n�q�A�y���[���擙�C�O�ł̃C�J�ނ����ƃX�^�[�g�̒x��Ȃǂ�����ō�N������������ƁA���ł���B
�݁@�Ɂ@��
13�N�͑O�N����10.7���g���̂��Ȃ�d���ɂ���n�܂�A�㔼���͂���Ȃ�̏����Ō������݂��B�܂��A�V���̐��g�����n�܂���6���������ɏ��X�ɑ������A�{�i�����n�߂��H���ɂ͗�N�̂悤�ɍɂ��c����A��N�قǂł͂Ȃ��z�N�ɂ�8.5���g���ƑO�N�����Ȃ艺������B���ύɗʂ��A7.4���g���ŁA�قڑO�N�i7.3���g���j���݂ł������B
���@��@�n�@���@�ׁ@�ʁ@�Ɓ@���@�i
�X�����C�J�̏���n���חʂ́A��5.8���g���i�O�N5.4���g���j�A�Ⓚ1.5���g���i�O�N1.6���g���j�ł������B�{�N�͎Y�n�ł̋����O�N�ɂ͋y�Ȃ����̂̍D���ł��������ƂŁA�������������B�Ⓚ�͈��l�ɂ��S��炸���̑����ƁA����҂̐��n�D�������đO�N���݂ɂƂǂ܂����B
���i�́A��307�~(�O�N358�~)�A��258�~(�O�N261�~)�Ő��E��Ƃ��������X�����������B
���ɃC�J�͖��[���v�̌����������A����x�o�ł͋��z�A���ʃx�[�X�Ƃ������������ł������B
�m�y�C�J
13�N�̂m�y�C�J�ދ��́A��^�D�P�ǂ݂̂̑��ƂőO�N�i��Q�ǁj�������A262�g���őO�N1,087�g������������B�P�Ǔ���̋��l�ʂ�262�g���őO�N�i544�g���j��傫����������B
�m�y�C�J�̎Y�n���g�ʁi�S���A�j�́A519�g���őO�N�i1,434�g���j��傫����������B
���i�́A171�~�łS�N�����̕s���ɂ�������炸�A�O�N�i184�~�j����≺������B
�@�܂��A14�N�̏o���͂Ȃ��ɂȂ�͗l�B
�r�v�`�C�J
13�N�̂r�v�`�}�c�C�J�ދ��́A�`�q31�ǁ|44,041�g���i�O�N31�ǁ|85,012�g���j�A�e�n�q14�ǁ|18,176�g���i�O�N15�ǁ|20,488�g���j�ASA���C33�ǁ\7,675�g���i29�ǁ\9,317�g���j�ł��������A�������̌����̒x��ŋ���ւ̓�����x��A���C�A�t�H�[�N�����h�A�A���[���`���Ƃ������g���A�P�Ǔ�����Ƃ��������݂��B
�@�Y�n���g�ʁi�S���A�j�́A53,139�g���őO�N�i88,012�g���j����������B
���i��150�~�őO�N�i138�~�j�����������B�{�N�́A���g���͌����f���S�N�����̈��l��E�p�������A�{�`�����X�����C�J�̂���Ȃ�̍D���������āA�啝�ȏグ�ɂ͌q����Ȃ������B
�A�J�C�J
�{�N���A�����������甪�ˑD�c�𒆐S�ɔ��فA���D�c�̑�^�E���^�����D�͐ԃC�J���Ƃ��݂�ꂽ�B���N�̋����͋��������̉ď�Ɉꎞ�I�ɋ����܂Ƃ܂������A��N���l��������H����~��ɂ����Ēᒲ�ɏI��������ʁA�ߔN�ł��ł����Ȃ����g���ł�������N����≺������B�܂��A�{�N�͏��^�D����N�ȏ�ɂ݂�ׂ������Ȃ��A�ɒ[�ɏ��Ȃ����g���ɏI�n�����B�Ȃ��A��^�D�i�������Ɓj��24��2,981�g���ŁA�O�N�i22��1,418�g���j���������B
�S���A�W�v�ɂ��ƁA��111�g���i�O�N1,252�g���j�A��1.5���g���i�O�N1.6���g���j�ł������B
�Y�n���i�́A��55�~�i�O�N161�~�j�A��301�~(�O�N293�~)�ł������B���g���̌��������������Ă��邱�Ƃ������Ė{�`�����͌����������������B�ƊC�O�����̃T�C�Y�A�\�[�g������ɕ�A�s����2����̈��l�ɏI�n���^�R�Ƃ��āA�v���Ԃ�Ɂu�����v�ȂP�N�ƂȂ����B
�@�C�O�Ԃ����́A��ɍĊJ���ꂽ�y���[��̂ɃR�X�^���J�ł��������A�v�X�A33��-84,041�g���A1��-873�g���ŁA��N���сi27��-66,778�g���A29��-24,244�g���j���y���[������,�R�X�^���J�͑啝�ɉ�������B�Ȃ��y���[���C�ł��{�N�͑��Ƃ�12�ǂ�2,082�g���̋��l���݂��B
�@
�A���C�J
�@12�N�̗A���C�J�́A5.6���g���őO�N�i6.3���g���j����≺������B
���i�́A���㏸��422�~�őO�N�i388�~�j���������B
�Ⓚ�C�J�̎�v�A�����́A�A���[���`��122�g���i�O�N599�g���j�A�C���h1,872�g���i3,681�g���j�A��p318�g���i�O�N2,271�g���j�A����24,405�g���i�O�N20,963�g���j�A�����b�R2,904�g���i�O�N1,806�g���j�A�^�C7,138�g���i�O�N26,040�g���j�Ŗ{�N����N�Ɉ����������̑����X���������ł��������A�^�C�͑啝�Ȍ����ƂȂ����B
12�N�̗A�o�́A3.4��g���őO�N�i2.7��g���j�����������B�����12���\����1000�g���ȏ�̗A�o�����������߂ł���B
�����S�C�J
13�N�̃R�E�C�J�̗A���́A��3.9���g���O�N�i4.1���g���j����������≺����Ă���A�{�N���������Ă��肻�̌X���ɕω��͂Ȃ��B
���i�́A582�~�őO�N�i552�~�j�����������B
����n���חʂ́A0.9���g���ŗA���̌����▖�[���v�̔�������֕i������A�������O�N�i1.1�����j����������B
���i�́A769�~�ň����̌����f���đO�N�i715�~�j�����������B
���̃C�J�͖w�ǂ��Ɩ��p���v�ł��邪�A�N�X�\�f�C�J���̋������ނ�A���������i�Ƃ��Ă̑�֏��ނɎ���đ����Ă���A�N�X�������������Ă���B