2001年マアジ![]()
単位:数量、1000トン、価格、円/kg 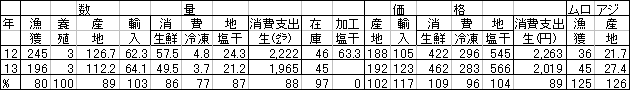
漁獲量と資源
13年の漁獲量は、20万トン前後と推定されるが、前年を下回る水準であり、近年ではやや低い水準の漁獲量となった。
本年は主体の東シナ海、山陰海域とも前年を下回るなどやや低調な漁獲で、上半期の盛漁期にはいずれの海域とも目立った漁獲の伸びがみられず、僅かに7月に山陰でまとまった漁獲をした程度であった。
主力の東シナ海及び日本海沿岸で主に漁獲される対馬暖流系群は、1980年代以降増加傾向を示し、1990年代の中盤は高い水準を維持した。しかし99年,2000年とやや減少しており、水準としては中位といわれている。
また太平洋系群は1982年以降一貫して増大、特に1990年代中ごろ高く安定していた。しかし加入量の減少により1997年以降資源量は減少に向かったが、再度2000年には加入量の増大がみられ、現在資源は中水準で減少傾向にある。
以上のように何れも資源水準は中位であるが、今後の資源の安定的な管理には、産卵主群である2、3、4歳魚=親魚の確保の必要性が依然必要であるとともに、ともに主産卵場である東シナ海の諸外国との共同管理も極めて重要且つ必須の課題として取り組む必要がある。
ムロアジ類
本年のムロアジは、前年より漁獲が上回ったものの依然資源状況の目立った回復はみられて
おらず、近年でも昨年に続いて低い一昨年並みの漁獲にとどまったものとみられる。
(近年MAX:H2年 10.9万トン)
産地水揚量と価格(42港)
海域別水揚量 月別漁獲量 月別価格推移

13年のマアジの水揚量は、11.2万トンで前年(12.7万トン)を下回った。
九州西方海域では、春の盛漁期(4〜6月)に殆ど漁の山場がみられず、秋口にも上昇することなく平板なまま終漁となり、水揚げは前年をやや下回った。
また、山陰沿岸では7,8月に漁獲がややまとまったものの、秋口には10〜12月には極端に落ち込み、昨年をやや下回る水揚げに終わった。また、総漁獲量でも東シナ海を下回った。
太平洋側では薩南海域が好調で、東海、南西、房総海域を含め昨年を上回った。
魚体は、東シナ海では100g以下のアジが35%(前年31%)(70g以下の豆アジは全体の22%:前年8%)を占め主体であり、魚体の小型化傾向が一層顕著であった。
山陰沿岸でも、依然、魚体の大きいマアジは少なく豆アジ(0〜1歳魚)主体で、僅かでであった。
価格は、192円で前年(188円)を僅かに上回ったが、魚体も小さく大幅な上げにはならなかった。
輸 入
13年のアジの輸入は、6.4万トンで5〜7万トンの近年の範囲内の内ではやや高水準であり、前年(6.2万トン)をやや上回った。
本年は、オランダ2.3万トン(前年:2.2万トン)、ノルウェー0.3万トン(前年:1.7万トン、アイルランド1.9万トン(前年1.1万トン)で再度アイルランドが伸び、逆に昨年大幅に伸びたノルウェーの減少が目立った。韓国は0.4万トンで前年(0.4万トン)並みであった。
本年は、国内漁の3年続きの低迷が大きく、依然の輸入意欲が強かったことが反映したものとみられる。
価格は、123円で前年(105円)を上回ったが、為替円安と海外産地での上昇の影響が強かった。
在 庫 量
本年の在庫量は、4.5万トンと前年(4.6万トン)をやや上回った。
これは、国内生産量の減少が、輸入量の増加をカバーしきれなかったことと、魚体の小型化が顕著で、総じて餌に向けられる割合が多かったものの、餌料の回転も速かったこと事の反映とみられる。
消費地入荷量と価格
13年の消費地入荷量(10大都市)は、産地での水揚げ減少もあって5.4万トン(生5万トン、冷0.4万トン)、前年6.3万トン(生5.8万トン、冷0.5万トン)を下回った。なお、塩干は2.1万トンで前年(2.4万トン)をやや下回り今年も漸減傾向が続いた。
本年は産地での魚体も小さくその結果入荷が少なくなったが、消費支出も数量、金額とも減少しており、10%強の減少であった。
価格は、生462円(前年422円)、冷283円(前年296円)、塩干566円(前年545円)であったが、生鮮・塩干が入荷減少を受けて上伸したが、冷凍は下落した。