2000年の主要水産物の需要と供給
単位:数量,1000トン、価格,円/kg
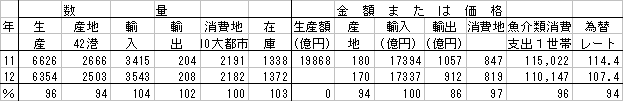
数 量
TAC制度も定着しつつあるが、本年の産地水揚量(統計情報部集計による全国42産地漁港)は、250万トンで本年も引続き前年をやや下回り減少傾向が続いた。
全体的に資源減少傾向が顕著な中で、本年も水揚げの増減幅が大きかったのが特徴であった。
大きく増加した魚種は、セーフガードの議論にまで発展したカツオ(生、冷)を始め、サンマ、生鮮スルメイカ、冷凍アカイカ、天然ブリ類、サワラ類などであり、大きく減少した魚種はビンナガ(生・冷) 、マイワシ、ムロアジ、遠洋イカ、コウイカ等であった。
輸入は、354万トンと引続き増加傾向であった。これは為替の円高傾向を反映した結果である。
この中で目立って増加した魚種は、話題になった活・蒲焼ウナギ、漁不振のイワシ、キハダ、現地漁が好調であったタコ、サバ、カツオ、サケ・マス、冷凍エビ類、イカ、ミール、ワカメ類であり、大幅に減少した主な魚種は、キハダ、メバチであった。
輸出は、約20.8万トンで円高環境もあったが、前年(20.4万トン)をやや上回った。
本年は、好漁であったもののカツオが東南アジア(タイ主体にフィリピン)向けが世界的な供給増加と需要の減少により昨年を大きく下回ったが、アキサケが再度増加したのが目立った。
消費地入荷量(10大都市)は、218万トンでほぼ前年(219万トン)並みであったが、近年の減少傾向は今年も続いている。
目立って多くなった魚種は、生鮮ではカツオ、天然ブリ、タチウオ、クルマエビ、冷凍では昨年同様ニシン、輸入の多かったタコで、大きく減少した魚種は、産地水揚げの少なかったマイワシ、サバ類であった。本年は生鮮物・貝類が横ばい、海藻類、塩干品が若干減少し、冷凍品がやや増加した。
在庫量は、月平均137万トンで前年(134万トン)を上回った。これは、国内生産量の減少が依然進行したが、引続き円高もあって輸入が好調さを維持したことと、国内消費の低迷が反映しているものとみられる。
価格・金額
12年の産地価格は、170円で前年(180円)をやや下回ったが、サンマ、サバ類、スルメイカ等の多獲性魚種が総じて安値推移が目立ったことによるものである。
目立って高かったのが漁不振のマイワシ、メヌケ類や生アカイカ、で生ビンナであり、その他の魚種については概ね前年並みかやや弱含みで推移した。
消費地価格は、819円(10大都市)で前年(847円)をやや下回った。
目立って高くなった魚種は、2年連続のサンマ、漁獲不振のサバ類、冷凍キハダに代表される冷凍マグロ類であった。
逆に安くなった魚種は、カツオ、天然ブリ、ウナギと話題に上った魚であり、冷凍品ではスルメイカを始め、タコ、サバ類と輸入の多かった(輸入価格の下げた)魚種であった。
輸入金額は、1兆73337億円で引続き前年を57億円下回った。
輸出金額は、1418億円で前年(1184億円)を下回った。
円 レ ー ト
12年の円レート(対USドル)は、年平均107円で前年(114円)より7円の円高となった。
円レートは、85年の9月のプラザ合意以降一時的な円安がみられたものの急速な円高・ドル安傾向が10年間続いた。
しかし、95年秋から円安に転じ、97年以降に証券会社、銀行の倒産が続き金融システム不安等も重なり一層円安が進行し、98年も一時140円台の安値を記録するなど秋口まで円安が進行した。その後、一時年末にかけて円高(113円)へと反騰したが、99年は夏場までやや円安(114〜121円)で推移したが、下半期には急激に円高に反騰し、12月は103円まで急騰した。2000年は年末の円高の103円からスタートであったが、その後は一時的な円高はあったが、基本的には円安傾向で推移し、年末には111円まで下げた。
(参考:84年237円→85年240円→86年170円→87年146円→88年128円→89年137円→90年145円→91年135円→92年127円→93年112円→94年102円→95年94円→96年108円→97年121円→98年131円→99年114円→2000年107円)
石 油 価 格(1kl当たり)
12年のA重油価格は、前年末からの28,500円の高値から始まり、3月中旬には29,000円に上昇、その後5月中旬まで29,500円で推移した。しかしその後5月中旬に28,000円に下落、この価格が9月下旬続いた。そして下旬に30,000円、10月中旬31,000円まで上昇、12月に入って更に33,000円まで上昇し年末を迎えた。
参考:近年の最高値74,000円/kl(1982年11月)