00年マアジ
単位:数量、1000トン、価格、円/kg 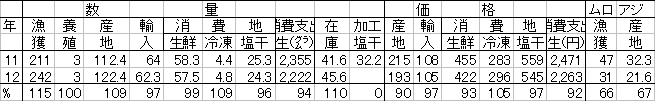
漁獲量と資源
12年の漁獲量は、24万トン強と推定され、前年をやや上回る水準であったが、近年ではやや低い水準の漁獲量となった。
本年は主体の東シナ海でやや多かったものの、山陰海域ではやや低調な漁獲となり、盛漁期にも5月を除いて目立った漁獲の伸びがみられず、下半期も低調で周年を通じてピークのない平板な漁況にとどまった。
主力の東シナ海では1980年代前半まで資源が低水準であったが、その後増加傾向を示し、近年は比較的良好な水準にあると言われている。その結果、0,1年魚の加入もあって漁獲は増加・安定傾向にあったが、本年も昨年に続いて漁獲の低迷がみられ、比較的安定しているものとみられていた資源量に、この数年間で産卵量・卵稚仔の生き残り等も含めて何らかの変化があったことが予想される。したがって漁獲の減少・低迷からみても、また従来から言われているように、産卵主群の2、3、4歳魚の親魚の資源は依然低い水準であり、本年はそれに加えて若齢魚の漁獲=加入も依然極めて少なかった。
日本海の資源は93〜95年以降漸減傾向にあって、99年級群は98年級群とともに低い年級とみられており、2000年級群の加入も99年級群より低いとみられている。
ムロアジ類
本年のムロアジは、やや資源状況が悪化しているものとみられ、近年で最低の漁獲にとどまったものとみられる。
(近年MAX:H2年 10.9万トン)
産地水揚量と価格(42港)
海域別水揚量 月別漁獲量 月別価格推移

12年のマアジの水揚量は、12.2万トンで前年(11.2万トン)をやや上回った。
九州西方海域では、春の盛漁期(4〜6月)の漁が本年は5月に若干山場がみられたことで、秋口には極端に低調となったが、水揚げは前年をやや上回った。
また、山陰沿岸では5月に漁獲がまとまったものの、秋口には11,12月にややまとまった程度で、山のない漁で昨年をやや下回る水揚げとなった。したがって、総漁獲量では東シナ海を下回った。
太平洋側では東海、南西、房総海域とも昨年以下のやや低調な漁が続いた。
魚体は、東シナ海では100g以下のアジが31%(前年30%弱)(70g以下の豆アジは全体の9%:前年13%)を占め主体であったが、前年に比べると豆アジの割合がやや減少している。山陰沿岸でも、依然、魚体の大きいマアジは少なく豆アジ(0〜1歳魚)主体で小以上が15%程度であった。
価格は、193円で前年(215円)をやや下回った。これは42港ベースで見ると水揚げの増加を反映したものとみられる。
輸 入
12年のアジの輸入は、6.2万トンで前年(6.4万トン)をやや下回ったが、近年の5〜7万トンの範囲の水準の中ではやや高かった。
本年は、オランダ2.2万トン(前年:2.2万トン)、ノルウェー1.7万トン(前年:1.3万トン、アイルランド1.1万トン(前年1.7万トン)でノルウェーの台頭が目立った。韓国は0.4万トンで前年(0.3万トン)を若干上回った。
これは、国内漁の2年続きの低迷、為替円高と依然加工筋の輸入意欲が強かったのが反映したものとみられる。
価格は、105円で前年(108円)を若干下回った。
在 庫 量
本年の在庫量は、4.6万トンと前年(4.2万トン)をやや上回った。
これは、国内生産、輸入量とも供給ベースでは大きな変化はみられなかったものの、生鮮も含め需要がやや落ちてきたことを反映したものと見られる。
消費地入荷量と価格
12年の消費地入荷量(10大都市)は、産地でまずまずの漁を受けてで6.3万トン(生5.8万トン、冷0.5万トン)、前年6.2万トン(生5.8万トン、冷0.4万トン)並みであった。なお、塩干は2.4万トンで前年(2.5万トン)をやや下回り依然漸減傾向が続いている。
本年はマアジ自体の需要がやや低迷した結果、消費支出も数量、金額とも減少しており、冷凍がやや伸びた程度であった。
価格は、生422円(前年455円)、冷296円(前年283円)、塩干545円(前年559円)であったが、上述のように需要の減退により下落が顕著であった。